| 名称 | 日蓮宗 |
| 宗祖 | 日蓮聖人 貞応1 1222年~弘安5 1283年 |
| 開宗 | 建長5年4月28日(鎌倉時代 1253年) |
| 本尊 | 久遠実成本師釈迦牟尼佛 くおんじつじょう ほんし しゃかむにぶつ |
| 経典 | 妙法蓮華経(法華経) |
| 題目 | 南無妙法蓮華経 なむみょうほうれんげきょう |
| 教義 | お釈迦様の説かれたお経の中の真髄は「法華経」・法華経の一切は「南無妙法蓮華経」のお題目に集約されるとし、この法華経とお題目を広げることによって、命のある一切の救済を目的とする。 |
| 寺院数 | 5178ヶ寺 (平成18年調) 総本山は山梨県の「身延山 久遠寺」。 |
| 僧侶数 | 8275人 (平成18年調) |
| 信者数 | 約385万人 |
名称
日蓮聖人。
本尊 久遠実成本師釈迦牟尼佛
久遠実成の本師釈迦牟尼佛とは「お釈迦様」であるが、2500年以上以前にインドに誕生し、80歳でお亡くなりになった歴史上のお釈迦様ゴータマ シッタルタではなく、過去・現在・未来の三世に存在する永遠の存在であるお釈迦様の意味です。
日蓮宗の本尊を「日蓮聖人」であると誤解している方もありますが誤りです。上記のように本尊は永遠の存在であるお釈迦様で、日蓮聖人は、このお釈迦様の教えである法華経を、仏の使い(仏使)として我々に伝えてくれている立場です。 この差異については日蓮正宗の項を参照。
本尊の形態・姿
上記のように本尊は三世に常住のお釈迦様であるので、その姿を形として示すことはできない。従って日蓮聖人が体得された永遠なるお釈迦様の救済の世界観を文字(紙幅)で表現したものが大曼荼羅ダイマンダラ本尊です。
形態としては文字(紙幅)で表現したものと、それを木像で表したものがある。寺院では木像本尊が多く、一般在家では紙幅の本尊が多い。
(日蓮宗の公式ホームページ)
経典 妙法蓮華経(法華経)
新居日薩 アライニッサツ
法華経28品(章)の教説を前判(14品)の迹門シャクモン、後半(14品)の本門ホンモンに分け、この両者は立場の異なる人に説
かれたもので、あくまでも優劣があるとする見方を勝劣派とし、相違は認めるも最終的に思想的には一致するとする見方を
一致派と称した。
中国の天台智顗は迹門を体(核)とし、本門はその働き(作用)と見て、本迹の一体を主張。これに対し日蓮聖人は本門中心の法華経観のもと唱題受持成仏を主張するが、迹門の理念がそれを支えているのであると見る。
即ち、天台智顗は迹門がメインで本門は脇役(迹面本裏)に対し、日蓮聖人は本門がメインで迹門は脇役(本面迹裏)であると見たのである。
日蓮聖人歿後、この本門・迹門のとらえ方をめぐり種々な論争が起こり各派の分裂に至った。
本迹一致派 - 身延系諸派(身延派・池上派・中山派・妙顕寺派・本国寺派) この考えが今の日蓮宗となっている。
本迹勝劣派 - 八品派、妙満寺派、本成寺派、本隆寺派、興門派
昭和38年、祖廟(日蓮聖人の墓)を中心にして各派が連合し、日蓮聖人の理想を実現するために組織されたもので、参加している各派は以下の通りである。
日蓮宗・顕本法華宗・法華宗陣門流・真門流・本門流・日蓮本宗・本門法華宗・本門仏立宗・日本山・不受不施派・国柱会
日蓮聖人の弟子 日興ニッコウ(1246-1333)を開祖とし、富士の大石寺を総本山とする宗派。富士門流を源とし、興門派、大石寺派とも称したが、明治32年に本門宗と改称。明治33年、大石寺が本門宗より離脱し日蓮宗富士派と称したが、明治45年に日蓮正宗と公称し現在に至る。
勝劣派に属するが、特異な教義に「日蓮本仏論」がある。平易に示せば、世間が乱れている末法では釈尊の力は及ばず、(釈尊はリタイヤして本仏ではない)日蓮が本仏として人々を救済できるという主張。そして、釈尊が説かれた法華経は既に旧式の教えで、日蓮聖人の書かれたもの(遺文)が現代の法華経にも相当するとしている。
インドに誕生の釈迦(=釈尊)は真の救済本仏の仮の姿で、鎌倉時代の日蓮聖人こそが救済本仏の再誕生であると考えている。この教義は大石寺9世の日有(1409-1482) 26世の日寛(1665-1726)により確立された。これに対し日蓮宗は、あくまでも釈尊の存在と救済を三世に認め、日蓮聖人を上行菩薩の再誕として釈尊の教えを伝える仏使として尊敬している。
尚、日蓮正宗の信徒団体に創価学会があるが、平成4年日蓮正宗側から破門され、現在は絶縁状態にある。
仏教全てには信じ守るべき三つの存在(三宝 仏・法・僧)があるが、日蓮宗と日蓮正宗の三宝を比較すれば下記の通りである。
日蓮宗の三宝 日蓮正宗の三宝
仏-釈迦 仏-日蓮
法-法華経 法-本門戒壇の大本尊(大石寺の板曼荼羅)
僧-日蓮 僧-日興(大石寺歴代とも見る)
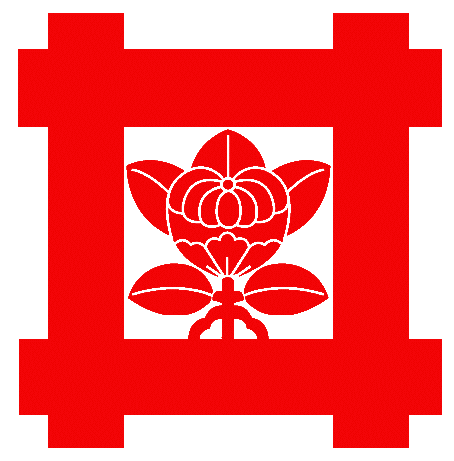
曼荼羅とは梵語のマンダーラ(本質・精髄等)の音写で、仏の悟った境地を図顕したもの。日蓮宗では日蓮聖人が「日蓮が魂を墨に染めながして書きて候ぞ」と体得信解した法華経による救済の世界を紙面に表したものである。
中央に南無妙法蓮華経のお題目、その左右に釈迦如来・多宝如来、その外側、中段、下段に十界にある存在を記している。この意味は十界にある全ての人々が、霊鷲山lリョウジュセンに於いて釈尊が説く法華経・お題目を聞いている(釈尊が法華経を説いている)ことを図顕したもので、お題目から伸びている独特の筆法は光明点(俗にヒゲ題目)と称し、過去・現在・未来の三世わたって十界の全てをお題目が照らし救済している事を意味しています。一口説法「光のイメージ」参照。
この形での曼荼羅は文永10年7月8日に始めて佐渡にて描かれ(佐渡始顕の本尊)、現在120余りの真筆本尊がある。
日蓮宗では臨滅度時の大曼荼羅(弘安3年3月に日朗上人に与えられたもので、日蓮聖人臨終の枕頭に掲げられたもの)を宗定と定めているが、他の全ての曼荼羅本尊にも等しく衆生救済の願いと功徳があり、宗定のものと相違するものではない。菩提寺住職から授与されたものも等しくこれに準ずるものである。
尚、日蓮正宗では大石寺に掲げられている大曼荼羅(俗に板曼荼羅)が唯一絶対とし他のものを認めていない。
仏教の世界観の一つ。迷いと悟りの世界を10に分類するもので、地獄界・餓鬼界・畜生界・修羅界・人間界・天界・声聞界・縁覚界・菩薩界・仏界の10の世界を示すもの。
地獄界・餓鬼界・畜生界・修羅界・人間界・天界→生と死の世界を輪廻転生する迷いと苦しみの世界(六道)
声聞界・縁覚界・菩薩界・仏界→上の六道を離脱(解脱)した聖者の世界。(四聖)
日蓮聖人は天台智顗の教説より、十界の中の一つの世界には、同時に他の九界も存在する。お互いが互いに他の世界を持あって存在しているという十界互具ジッカイゴグを説いた。即ち、地獄界の中にも他の餓鬼界から仏界までの全てが存在しているので、地獄の衆生も菩薩や仏になることができる。人間界の凡夫が仏になる(成仏)ことができるのは、人間界の中にも仏界が備わっているからである。(また、同時に人間も地獄や餓鬼・畜生界の存在となることもあるのである)
地獄界--地下の牢獄のような苦が最も重い世界。
餓鬼界--飲食を求めても求められない苦の世界。
畜生界--互いに貪りあう痴・愚の世界。
修羅界--闘争、怒り世界。
人間界--苦と楽が半々である世界。
天界---優れた楽の世界だが苦もある世界。(帝釈天・毘沙門天等)
声聞界--仏の声を聞いて悟りを得る声聞の世界(小乗の悟り)
縁覚界--師がいなくても悟りを得る縁覚の世界(小乗の悟り)
菩薩界--他者と共に悟りを得るため修行する菩薩の世界。上求菩提下化衆生の世界。
仏界---悟り(大乗の悟り)を得て、他者を導く仏の世界。
智顗 ちぎ
中国の南北朝時代から随にけての学僧(537~597)。インドより中国に伝わった多くの経典を分類・整理して、法華経を最大一とした天台宗を開いたので、天台智顗・天台大師・智者大師とも尊称される。
代表的な著作に法華経の解釈書である『法華文句』『法華玄義』『摩訶止観』がある(天台の三大部と言う)。尚、日本で一般的に天台大師と言われているのは、日本天台宗の祖である最澄(伝教大師)である。
「浄土と云うも地獄と云うも外には候はず、ただ我らが胸の間にあり、これを悟を仏と云う、これに迷うを凡夫と云う」