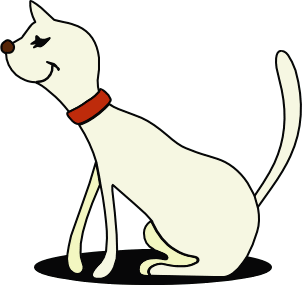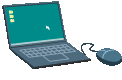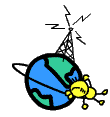平成8年頃からsaddharma mailというメールマガジンを檀家の方などへ発信しています。内容はお寺の出来事、社会の出来事に対する感想、ちょっとした法話等々。住職の100㌫勝手な言いたい放題です。
Saddarma mail from Houzenji No
109 2011.5.13
前号は昨年末でしたのでだいぶご無沙汰をしています。信州もようやく新緑となりました。3/11に東日本大震災があり、多くの命が非情無念にも失われました。今年の新緑が悲しくもその場に在るのが運命であった諸霊への捧げとなり、また、ある意味で死よりも辛く残酷な現実の生とならざるを得なかった多くの方への希望の力となる新緑であるを願っています。各地で復興に向けての募金等々が行われています。原発の災難もさらに重なり、当たり前の日常への道は果てしなく遠く、心の痛手の癒される時はいつになるのでしょうか。日本人は地震の巣の中に一角を一時の間借用しているようなもので、決して対岸の火事ではありません。自分の家族・親族の出来事として祈り、そして可能な協力を心掛けたいと思います。
我々凡人の祈りは往々にして自分を中心とした一人称や二人称の祈りが多いのではないでしょうか。自分のため自分の先祖のため、家族のため等々。しかし、先に逝った顔も知らない人々のために、見ず知らずの方々の幸いのためにと祈る事は少ないのでは。。。我々の信ずる仏教、特に日本に広まった大乗仏教(個人的悟りの追求でなく、多数無限の方の悟りのための仏教)は他のためと言うこの考え方です。自行化他ジギョウケタ、忘己利他ボウコリタ等の言葉はこれを示しています。
一人称や二人称の祈りや願いは誰もがする願いですが、果たして仏さまはこのような祈りをお聞き届けになるのでしょうか。「何だ!自分のことしか考えていないじゃないか」「身勝手なやつだ」と思っているような気がします。御自分の先祖のため、我が家族のために祈った後で、震災で無念の最期を遂げた方々に、そして苦難の人生を受け入れざるを得なかった人々にも、仏さまの慈悲の光明が当たりますようにと祈りたいと思います。
******************
1食10円募金のおすすめです。
一日3回我々は無事に食事を頂いています。当たり前のような事ですが、この当然の事が当然でない国や人々が大勢います。食事の度に10円を素直に「ありがたく食事ができました」と感謝の気持ちを込めて、家庭で作った募金箱に募金をしたらどうでしょうか。この事は既に他の宗教団体で実施している事ですが、よいと思うことは見習ってもいいと思います。
一日で30円、4人家族なら120円。一月で3600円。一年で43200円。これを家族で相談して他のために有意義に考える。災害義援金に国際難民救援に等々、、幸せの「おすそわけ」です。方法を考える事自体にも他への思いやり・慈悲の心が養われるのではないかと思います。一人一人が食事をできた事に感謝し、10円を捧げる、供養するところにも意義があるので、「お父さん今日の分まとめてお願い」ではその意義も半減してしまいます。ご家族で考えて見て下さい。でも「めぐんであげる」という気持ちでは汚れた10円となってしまいます。仏さまは見ていますよ。家庭の募金箱から暖かな仏さまの光が世界を照らしてくれる事を願っています。
*********************
.「国際グラフ」6月号に当山の記事が掲載されますのでご覧下さい。5/26に担当者と大仁田厚氏が来寺し、寺のことや今後の宗教等々らついてのインタビューが一時間半ほどあり、この概略と写真が掲載されます。電話にて取材依頼があり少々驚きましたが、ホームページを見ての取材という事で、日蓮宗の寺も過去数回取り上げられているようです。
観光寺院ではないのでマスコミへの露出はブラスとマイナスの両面があって、始めは躊躇していましたが、今後はお寺も広報宣伝の時代と取材に応じた次第です。ゲラを見たのですが、さすがはプロで上手にまとめていました。
**************************
6/26まで上野の国立博物館で「手塚治虫のブッダ展」が開催されています。お釈迦様の生涯をマンガで描いた手塚治虫の「ブッダ」は若い時に何度も読んだものです。この映画も「ブッダ 赤い砂漠よ!美しく」として現在上映中ですので、こちらもご紹介します。
http://wwws.warnerbros.co.jp/buddha/
手塚氏の「ブッダ」はブッダの生涯を歴史に忠実に描くというものではなく、氏の中の「ブッダ」として描いているものですが、仏教の生死・運命・闘争・平和等の精神は作品の中で昇華されています。「手塚治虫のブッダ展」は仏教遺跡や現実の資料を展示しながら、氏のマンガを紹介しているもので是非見たいと思っています。機会を作って見てみませんか。800円です。http://www.budda-tezuka.com/outline.html
添付写真は「新緑の境内」
Saddarma mail from Houzenji No110 2011.7.25
境内も新緑から盛夏の濃い緑になり、雑草も元気にのびて草取り草刈りの時期です。だいぶ以前より朝のお参りの方が少しずつ草取りをして下さっているので大助かりで感謝しています。今年は「花オクラ」を玄関前に植えましたので花が楽しみです。昨年はこの花びらを食べることができると言うので食べてみましたが、「旨い」というよりも自然大自然の味というところでした。それでも、あまり食べないので今年は皆さんも食べてみてはどうですか。
パソコンをノート型のwindows7に取り替えました。データの移行や新しい操作等でまだ慣れずに70㌫というところでしょうか。と言っても設定等は全て倅の副住職任せでしたが。。メールは何とかできるようになりましたが、ホームページのアップは使っていたホームページビルダーがかなり旧式のものでしたのでこれからです。もしかしたらホームページは古いパソコンで使わざるを得ないかも・・少々情けない次第ですが。。。 機械器具は慣れるが肝心で暫くはpcと格闘となりそうです。
前号に1食10円募金についてお薦めしました。我が家でも少し大きなビンに「1食10円募金」とラベルをつけて食卓に置きました。ところが、目下のところ実行しているのは小生のみで少しいらついています。顔を見るたびに「10円」と言うのですが「後でまとめて入れるよ」と何ともそっけない返事。皆さんのところはどうですか?趣旨を説明して是非とも実施してみて下さい。
8/3水曜日は御施餓鬼大法要です。お誘いあってご参詣下さい。檀家以外のお友達もどうぞ。大歓迎です。
9時 受付
9時半 護持会総会 諸報告など。
10時15分 法話-大橋一雄師(大町市 妙心寺住職 長野県布教師会長)
11時半 御施餓鬼法要(約1時間20分の予定)
例年、昼食の後に法要となっていましたが、小生の体調もあり、また暑い時期でもあり、できるだけ短時間となるように考慮して、今年は法要の後に昼食弁当をお渡ししますのでお持ち帰り願うようにいたしましたのでお含み下さい。
この法要は、お盆の前に行われるためご自分のご先祖供養のためのものと思われますが、その意味の外に本来の意義がありまするる。それは全ての生命(人間・動物・植物等)に対する報恩感謝と供養の意味です。直接、自分の知らない多くの生命によって我々は生きています。これを仏教では縁起とか因縁とかと言いますが、平易に云えば関わり合い・関連性とも云ってよいと思います。
自分知らない第三者、動物や植物など命のある存在は、どこかで必ず見えない線で関係づけられています。そのおかげで我々はここに存在しているのです。例えてみると、インターネットの無数の回線が、自分では知らなくとも世界中に張り巡られ関連を持っているようなものでもあります。見も知らず顔も見らぬ多くの人々、多くの動植物との関連性で我々は生きています。生かされていると云ってもいいでしょう。
ですから、お勤めや法要の後には必ず「願わくばこの功徳をもって、普く一切に及ぼし、我らと衆生と皆ともに仏道を成ぜん」という言葉を加えるのです。仏教徒の本当の祈りは、決して我がためのものだけてはなく、多くの人々多くの命のために祈ることでする
今年の御施餓鬼には東日本大震災で非業の死を遂げざるを得なかった多くの霊に新盆の供養を捧げたいと思います。
第2回の法善寺寄席のお知らせ。
期日9/18日曜日
時間午後2時か3時より。詳細は後日報。
出演 地元出身の三遊亭鬼丸さん。
場所 法善寺の本堂。
会費 なし。
お寺でにぎやかに笑ってみませんか。笑いはストレス発散でもあり、ユーモアは心を和らげ、人間の免疫力も高めるのだそうです。また人生のスパイスとも云われています。どなたでも結構ですのでお誘いあってご参加下さい。
添付の写真は「半夏生」と「フウセンカズラ」
Saddarma mail from Houzenji No111 2011.9.9
残暑お見舞い申し上げます。御施餓鬼、お盆が無事におわり、寺もようやくいつもの静けさの日常にもどりました。しかし、この数日は全国的に温度が下がり、20度程度の陽気で長袖が欲しいほどです。今年86歳になる母宅にはコタツがあり、今年は収納の予定がありません。たぶんこのままでしょう。母の姿を見ていると、不如意な足をジット見つめ「動け 動け」と呟いているのを見ると、老いの厳しさ・辛さを・切なさ・淋しさをしみじみと感じます。
ついに母も介護を要する事となり、申し訳ないと思いながら寺の都合等でショートステイも利用している。今までも老いについていろいろと法話等で語ってきたが、自己のものとなると、受ける思いはかなり感情的にもなり「親は百人の子を養えども、子は一人の親を養うこと難し」「老いたるを敬うなりは人倫の道なり」「母の恩は大海の海より深し」「我が頭は父母の頭」等の日蓮聖人遺訓に申し訳なくも、不穏当なる言葉を吐き、忸怩たる思いしきりで、せめて「何もすることなくば一日に二度三度ほほえみを母に与へよ」の遺訓だけは心したいと思っている。今まで、檀家等の皆さんの「老い」についての相談にはいろいろと考えて答えてきましたが、自己のこととなると、だらしなくもどうしてよいやら皆目わからなくオロオロするのみです。「天の加護成きを疑はざれ、現世の安穏ならざるを嘆かざれ」を心に、これ「全て仏道修行」と思い過ごしているこの頃です。お笑い下さい。。
------------
7月に1回、8月に1回蜂に刺されました。いずれも「黄色スズメ蜂」。以前から少々気になっていた玄関脇の灌木の剪定を始めたところ、左手の甲にチクンと正に刺すような痛みが走り、続いて右頭部にチクリ。蜂に刺されたら先ず毒を絞り(吸い取り)しかる後に塩をすり込めと承知をとていた処ですが、その場所が何とも絞るに絞れない処。
蜂の刺されは数日間腫れるのは承知ですが、葬儀が迫っていたので、とりあえず外科に急行し注射と軟膏で帰宅。4日間予想通りの腫れでしたが、薬のためか思ったほどひどり腫れずにいました。いつもは軍手に帽子は常用なのですが、、、間の悪いという時はこんなものですよ。ドクターが刺されたのは初めてですか?の問いに、まてよ・・前に刺されたのは・・・。そういえば子供の頃はよく刺されていたが、大人になってからは記憶がない。
お盆も終わりホット一息の時にまたチクリ。今度はアゴで台所の中。どうやら外から連れてきてしまい、蜂さん虫のいどころが悪かったようで一撃というところ。その時はシャツの上から鬱血するほど絞り、前にもらった薬を塗って、また病院へ。蜂に刺されて病院なんて以前はよほどの間抜けと笑われるところでしょうか。外科のトクターは「またですか。蜂が多いんですね。お宅は。。」この時はすかさずもらっておいた薬をぬったせいか腫れも軽微で、あまり目立ちませんでした。
2回となると、どこかに巣があるに違いないと刺された付近を捜索。ありました。玄関近く、1回目にやられた近くにまだ小さいのですが、立派な蜂の巣が。見つけてしまった以上、参詣の人に被害があってはならずに急遽「蜂天国」へ電話して社長さんに出動してもらい駆除完了となった次第。御施餓鬼の月(全ての生命に感謝する法要)なので心にそれこそチクリとしましたが。。。。
------------------
下記により第2回の法善寺寄席を開催いたしますので、お誘い合っておいで下さい。
期日9/18日曜日
時間午後3時より一時間ほど。2時半開場。
出演 地元出身の三遊亭鬼丸さん。
場所 法善寺の本堂。
会費 なし。
いろいろなホールで落語を聞くのもいいですが、寺の本堂という一寸違った雰囲気の場所で聞くのもいいのではないでしょうか。昨年から実施していますが、思った異常にマッチしていました。時間があったら住職(小生)のおまけのお話があるかもしれません。でも、これは未定の事です。


Sadahharma mail from HOUZENJI NO90 2008.3.17
弥生の3月も中旬でもうすぐ新緑の時期となります。世の中は相変わらずの混迷ですが、新緑を素直に希望の色と思いたいものです。
****************
新聞に領収書の宛名をどうしましょうかと店員さんに言われて「上で」言ったところ、宛名が「上出」となっていた、という話があり、この落語的話は本当かな?と思っていた。ところが最近、家人から似たような話しを聞き少々がっかり。テレビでもやっていました。
やはり「上で」と言ったらしいが、宛名がカタカナの「ウエ」となっていたので、漢字の上にしてくれと言ったらしい、そうしたら、ウエに横棒訂正で「上」になっていた。アルバイトの若者の対応であったらしいが、店の奥で主人らしい人がクスクスと苦笑模様だと言っていた。ご主人がちゃんと教えてくれたことを切に願っている。
領収の宛名を「上」にしろとは元来おかしな話であるが、この社会常識的ことを知らないこともまたおかしな事である。人様のことをあれこれ言う資格はないが、知らないとはかくも滑稽なる状況を呈することになる。しかし、知らないことはあるもので、小生なども顔から火が出るが如くの事もあるが、年の功で上手にごまかしてしまう。だが、内心は忸怩たる思いで、我が身の不明を恥じるのです。 正にいつになっても自重自戒の心掛けが肝要。。。。
******************
人生は終着駅に向かって進む列車の如くですが、リターンのない、再び始発駅には戻らない列車です。列車に乗せてくれるのは両親、そして多くの乗客が乗ってきて一時を過ごしてそして去っていきます。恩師、連れ合い、友人、子供、知人等々。網棚の手荷物には思い出、大切な伝言等々、時々、乗客の私はこの手荷物の中を確認したり、追加したり、捨てたりしています。
まだ見知りの乗客が沢山いますが、自分の終着駅が迫りアナウンスが聞こえてきます。知人とのおしゃべりもおしまいです。乗り換え駅には次の列車が待っています。それは仏界行きの列車です。どんなに忘れ物があって戻ろうとしても不可能です。安心して次の列車に乗り換えることができるでしょうか。網棚の手荷物は持って行けないのです。持って行けるのは乗り換え列車の切符だけ。この切符には「仏界行」と書いてあり、そして誰でもがこの切符を持っているのです。
終着駅を東京としてみると58歳の私は、高崎をとっくに過ぎて大宮の手前あたりでしょうか。この列車は途中までは特急ですが、後半は各駅停車でゆっくりと走ります。誰でも自分が思っている駅が終着駅だとう限りません。突然にあなたの切符は軽井沢ですよ、高崎、熊谷、大宮等と云われて、ビックリするかもしれません。日蓮聖人は「先ず臨終のことを考えてから外のことに精進しなさい」と云っています。
いざ乗り換えとホームに下り、この切符をもって速やかに乗り換えができるでしょうか。「アレどこだ」「確かにあったはずだ」とウロウロしていろと、仏界行きの列車は動き出してしまい、次の列車まで切符を探すことになります。ホームでウロウロしている事を「成仏できないで迷っている」と云うのでしょう。時々はこの乗り換え切符が確かにあるか、どこにあるかを点検したいと思いますよ。いまはお彼岸・・ちょうどよい時ではないでしょうか。。。。。
Sadahharma mail from HOUZENJI NO91 2008.5.3
89号に、「今年はカマキリの巣が高いところにある」と書きました。例年に比べてだいぶ高いところ、約1メートル近くにありました。そこで、大雪を心配したのですが、結果は「たいしたことはない」というところに落ち着きました。さてカマキリさんの眼鏡違いだったのでしょうか。
さに非ずと思います。今年積もった積雪を日記にて計算すると50~60センチ。つまり融けないでそのまま積んでおくと約50センチの高さになるという事になります。カマキリさんも多少の余裕をみて安全高度を約1メートルとしたとすれば大当たりといえましょう。カマキリは決して間違ってはいなかった。。。。。と思いました。昆虫の持つ特異な感覚と、それを見つめ続けた先人の知恵に脱帽です。
***********************
昨年の5月に猫が屋根裏で子を産み、大騒動をしたことを記しましたが、今年もしばらく前からゴソゴソと怪しい。網をはったりして怪しい所を塞いだのですが効果なし(大工さんにやってもらいました)。しかし、屋根に飛び移る箇所(立木)を確認したので、そこを押さえろとばかりに登れなく網をはってやれやれ。。。と思ったら、敵も(猫)もさるもので、なんと網をよじ登るのではないか。。。これではお手上げ。。と云ってはいられない。昨年のような大騒ぎはまっぴら。
もう数年間屋根には登らなかったのですが、意を決して登り、高さを忘れて徹底的に侵入箇所の捜索した結果、発見しました!。軒に張った網のわずかな隙間から侵入の痕跡(足跡と猫の毛があった)を確認。しかし、侵入猫は2匹。。2匹が屋根裏にいないことを確認しないと対処はできない。そこで、侵入確認の箇所に予め網やクギ、金槌等を用意してチャンスを狙うことにした。
しかし、いつも猫を探しているわけにもいかないので、なかなかチャンスは到来しません。猫の名前はジジとキキ。キキは比較的慣れているのでよく庭に見かれるのですがジジがいない。屋根を見ながら切歯扼腕の数日が流れた日、キキがとぼけた顔で庭の散歩。ふと車庫をみるといた!!。ジジが。庭にいた小生は携帯で家人に通報「2匹庭に確認!登らないように木の周辺を警戒せよ」。
その時は草履をはいたいたのですが靴に履き替えている余裕がない、草履のまま屋根に登って(梯子は数日前から屋根にかけていたのです)、予め用意の道具で徹底的に侵入防護、でも、眼鏡がずれてよく見えない。。アア老眼無情。。。でもペッピリ腰でなんとか完了しホット一安心。ついでに梅雨になる前の屋根掃除をしましたが。。。来年60才にしてはフットワークが良かったかと自我自讃。以来、2匹は地上生活。。。

Sadahharma mail from HOUZENJI
NO92 2008.6.24
中国四川の大地震、岩手の地震…多くの命が失われました。また、秋葉原にての理不尽な殺傷事件。。痛ましい思い出いっぱいです。この方たちのいわゆる非業の最期・横死の方々が、その生涯の最期に見たものは何であったかと思う時、いたたまれない思いとなります。誰でも願うことは、自分の愛する家族や、慣れ親しんだ景色や風でありたいと思うのだが(ここまで書いてきて、この文章をどこかで書いた記憶に気づいたのだか、どこへ書いたのかわからない)。御施餓鬼にはこれら非業の最期をとげた人々への供養も捧げたいと思っています。
生きていたいのに、非常な運命の力でこの世を去らねばならぬ命があるのに、2008.6/20の新聞に「自殺10年連続3万人」の記事があった。昨年は33093人が己の命を断ち、
その年齢は下記の通りとなっている。
60代以上 12107人
50代 7096人
40代 5096人
30代 4767人
20代 3309人
19以下 548人
60代以上が全体の36%、30代40代の一番の働きざかりが約30%だという。これらの原因は、仕事疲れ 子育ての悩み 健康(病気) 経済苦(生活苦) 家庭問題 男女問題 学校問題 孤独感等々があげられていた。自殺・自死といえば、人生や生き方家庭の問題等により若者や壮年層の問題という意識があったが、老年層にも至る深刻な問題となった。先日のテレビで90才の夫が85才の寝たきりの妻を介護している、所謂、老老介護がとりあげられ、将来への不安(経済的、、体力的など)から何度自殺へ心が動いたたかを語っていた。若者の自殺は、その因を正しく理解し、生きる意欲を激励しても向上させることができるし、何よりも前途の可能性を信ずることができる。これに対して老年層の自殺には、やりきれぬ思いのみが去来する。年金問題、格差社会等、安心できる将来を信じたいのだが。。。。
時代背景は違うが、若者の死について与謝野晶子の「君死にたもうことなかれ」がある。
これは旅順口包囲軍の中に在る弟によせての詩で、自殺とは全く異なる死についてであるが、命に対する思いは同じであろうと思う。この詩は戦時中には禁止になったと母が言っていたのを思い出しました。
ああおとうとよ 君を泣く/君死にたもうことなかれ
末に生まれし君なれば /親のなさけはまさりしも
親は刃(やいば)をにぎらせて/人を殺せとおしえしや
人を殺して死ねよとて /二十四までをそだてしや
堺(さかい)の街のあきびとの /旧家をほこるあるじにて
親の名を継ぐ君なれば/君死にたもうことなかれ
旅順(りょじゅん)の城はほろぶとも /ほろびずとても 何事ぞ
君は知らじな あきびとの/家のおきてに無かりけり
君死にたもうことなかれ /すめらみことは 戦いに
おおみずからは出でまさね /かたみに人の血を流し
獣(けもの)の道に死ねよとは /死ぬるを人のほまれとは
大みこころの深ければ /もとよりいかで思(おぼ)されん
ああおとうとよ 戦いに /君死にたもうことなかれ
すぎにし秋を父ぎみに /おくれたまえる母ぎみは
なげきの中に いたましく /わが子を召され 家を守(も)り
安しと聞ける大御代(おおみよ)も /母のしら髪(が)はまさりぬる
暖簾(のれん)のかげに伏して泣く /あえかにわかき新妻(にいづま)を
君わするるや 思えるや /十月(とつき)も添(そ)わでわかれたる
少女(おとめ)ごころを思いみよ /この世ひとりの君ならで
ああまた誰をたのむべき /君死にたもうことなかれ
とにもかくにも、死んではならぬという思いがにじみ出て、心がジンと熱くなる思いがする詩です。日蓮聖人の文章中にも命に対するものが沢山ありますので、以下に紹介します。当山のホームページにも載せてありますのでご覧下さい。
「..散りし花もまた咲きぬ。落ちし菓コノミもまたならぬ。春の風もかわらず。秋の景色もこぞの如し。いかにこの一事のみ変わりゆきて本のごとくなからむ。..『千日尼御返事」
「..命と申す物は一切の財タカラの中に第一なり。遍満三千界無有直身命と説かれて、三千大千世界にみてて候財も命にはかへられぬ事に候なり。されば命は灯火のごとし。食は油のごとし。..」『事理供養御書』
「..財なき人々もあり。財あるも財なきも、命とむ申す財にすぎて候財は候はず。..」
「..命と申す物は一身第一の珍宝なり。一日なりともこれを延ぶるならば千万両の金にもすぎたり。..」『可延定業御書』
「..一日の命は三千界の財にもすぎて候なり。..一日も生きてをはせば功徳積もるべし。あらをしの命や命や。..」
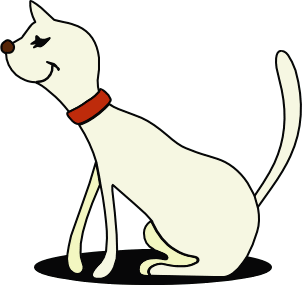
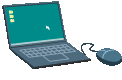
Sadahharma mail from HOUZENJI
NO93 2008.8.25
時は残暑お見舞いですが、このところ涼しいというよりも少々寒く、昨日は18度で長袖着用。夜は一枚薄いものを重ねるしまつ。83才の母はエアコンのスイッチを暖房に切替ていました。このまま秋になる事はないと思いますが・・まだ真夏ですよね・・日本では。。
****************************
御施餓鬼、お盆とと寺では一番ハードな時期を過ぎました 。 お盆の訪問には(当山は3年に一回訪問する地区毎のローテーションです)約130軒のお宅を巡回訪問しましたが、お経の後の会話は毎年悲喜ころごもです。就職、結婚、出産など、待ってましたとばかり笑顔で話し出す家。「お変わりありませんか」の問いに「それがねーお上人さん・・」と家人の病気や家業不振などの重い話をする方。どちらかと言うと、この暗い話の方が多いのです。
仏教ではこの現実世界を娑婆と言いますが、この娑婆の言葉は古代印度語で「サーハ」、サーハとは忍耐する場所「忍土」を意味します。正に現実の厳しい世界を示している端的な言葉です。どんなに辛い厳しい現実でも、この世に生まれた以上、これらから逃げたり回避したりは出来ません。眼前にある現実を正しく受け止め、どんな暗闇でも必ずある一条の光を信じて生きるしか道はないのではないかと思います。その時に娑婆の闇を照らしてくれるのが、一条の光の方向を指してくれるのが「お題目」です。どんな時でも希望を持って、光を信じてお題目を唱えたいものです。
********************************
松本サリン事件被害者の河野さんの奥さんが亡くなられました。河野さんも奥さんもさぞ無念であったろうと思いますが、テレビの報道の中で河野さんが語っていたお話の一部がとても印象的でした。奥さんに語ったという内容です。
「あなたは寝たきりで何もできないと思っているかもしれないが、決して何もしていないのではないよ。君がここにいてくれるから僕も子供達も生き甲斐があるんだよ」
最近、終末医療について延命措置は避けようという本人の意見も多いと思います。終末期の看取りには、決してきれい事では通らない、家族の実質的負担(精神的・経済的等)や心の葛藤があります。「頼むから死んでくれ」「もう回復しないで」という非情な心の声も現実には幾度か心の中に錯綜するかも知れません。難しい問題ですが延命拒否の考えには理解できる事も多々あります。命の灯火が自然に消えてゆくのを機械的に止めないでという思いは理解できます。
他方には、「とにかく生きていて」「いるだけでいい・息しているだけでもいい」という看取る立場の考えもあります。河野さんの場合、延命措置がとられていたかどうかは解りませんが、どんな命であっても、無価値な命はないという事は認識すべきことでしょう。
命に「価値」の言葉を用いるのは適切ではありません。価値は必然的にその質観にも言及し、「存在する事に足りる命と存在に値しない命」「必要な命と不必要な命」と発展してしまう危険があるからです。民族浄化と云うおぞましい言葉で、どれだけ多くの生命が消えていったかは歴史の語るところです。そんなに大げさに云わなくても「意識のないここにいるだけの命」をそれだけで否定してしまう事はできない、大事な存在理由があるのだという事を河野さんの言葉から改めて考えさせられました。
上記とは視点が違うのですが、河野さんの著書『命あるかぎり』に「私は、麻原被告も、オウム真理教の実行犯の人たちも、恨んでいない。恨むなどという無駄なエネルギーをつかって、限りある自分の人生を無意味にしたくない」という一文も大いに考えを深くするものです。ただし、出版社が第三文明社であることが少々気がかりですが・・。
*************************
日蓮宗新聞 「ひと口説法」より転写。「濁霧をはらう。」(高知県 本正寺 高橋誠昌師)
昨今、「競争原理」が第一の社会規範とされているが、それは所詮「弱肉強食」。畜生界の掟である。古来より人の世の掟が畜生界の掟でよしとされた例はない。今人々は、我欲を満たすことに懸命で、その耳には「夢を叶える」という心地よい言葉のみが響き、踏みつけた他者の声は届かない。
一方「夢の叶わぬ」者は、正体不明の憎悪と劣等感にかられる。秋葉原事件の犯人をかりたてたゆがんだ想念は、必ずしも特異とき言い切れぬところにこの事件の恐ろしさがある。
全てのものが互いに縁となり、ご本仏の大生命として息づいている、この世界の実相。今やそれは、末法の濁霧に覆い隠されている。その霧はあまりに深い。だからこそ、今こそ我々は声を惜しまず、まず南無妙法蓮華経と唱えつづけよう。互いに仏として敬いあう、真実の姿。その姿を覆い隠す末法の霧を晴らし、正気を取り戻そう。
******************************
寺のホームページは頻繁に更新や新情報がアップできるものではありませんが、十年一日の如くでは面白くも見たくもなくなるので更新には苦慮するところです。そこで、一計を考えて、最近流行のブログなるものを少々加味して「最近のできごと」なるページを作っています。4,5日毎に寺の出来事を少しずつ書いていますのでご覧下さい。これなら労せずして更新ができるというわけ。。。
Sadahharma mail from HOUZENJI
NO94 2008.11.4
前便は8月でしたので大分ご無沙汰をしております。お元気でしたでしょうか。今年もあと2ヶ月でお終いですが、寺は
これから落ち葉掃きで大車輪の時ともなります。毎年アーヤダナーと思うのですが、これまた御修行であり、落ち葉掃き
できる事を幸せと思って頑張りたいと思います。しかし銀杏の葉はまた厄介・・何と行っても焼却が困難ですので運んで
山の中に捨てざるを得ないのです。外の落ち葉は簡単に燃えるのですがネ。しかし、その実のギンナンは美味。えも言
えぬ臭いを、これまた修行なりと観念して折を見てこれを剥く日々。。何年も母がやって、そして今自分がこれを行ってい
る。これも一つの相続でしょうか。「法善寺ギンナン」道の駅で売ろうかーーーなーー。。。
******************************
10/25-/26当山青壮年会にて身延山へ参拝に行って来ました。初めて身延へ行った方が多く、その荘厳さに驚いたり
、長い石段に疲れたり、特別法要に感激したり、初対面の方とも親しくなったりと沢山の思い出と信仰の財産を得た旅と
なりました。
「人間時々はこんな体験が必要だよ」「今度は必ず家族を連れてこよう」の声が多くあって、この旅行も大成功だと信じま
した。しかし、この計画中に60代70代の方から「エー若い者だけなのー、私達はどーすんの」の声があり少々説得に苦
慮する場面もしばしあり困ったこともありました。今度は年齢制限なしで計画いたします。
************************************
先日レンタルDVDで「最高の人生の見つけ方」を見ました。主演はモーガン・フリーマンとジャック・ニコラウス。モーガン フリーマン
演ずる信仰心の厚い心優しい家庭人と、ジャック
ニコラウスが扮する離婚歴4回で無神論者の大金持ちが余命6ヶ月と宣言されてからの人生の有様を描いた映画。余命6ヶ
月と宣告されてから二人は「棺桶リスト」Bucket list(映画の原題)を作る。このリストは棺桶に入れる物のリストではなく
、棺桶に入るまでにしたい事のリストで、「他人のためによい事をする」「泣くほど笑う」「荘厳な風景を見る」などのものか
ら「スカイダイビングをする」「入れ墨を入れる」等々。
一人は大金持ちなので資金は潤沢、世界中にリストの達成のために乗り出して、その目的を成し遂げるべく最後の旅に
て出る。半分コメディーで半分はシリアス調とでもいうような映画。途中二人は、家族への愛、友情などを再認識してゆく
のですが、ラストは二人とも亡くなり遺盃をエベレストの頂上に埋める、つまり、一番荘厳な風景を見るというリストの達成
で終わる。秀作とまではいきませんが准秀作。おすすめです。
病名の告知は日本でも一般的になりつつあるが、余命を本人に告知る事は日本ではまだ時間を要するようだか、あと6ヶ
月となったら何を考え何をするのだろうか、何をすべきであろうか。。。死は年齢には無関係で自分のものになる。「なーに
なるようになるのさ」そうですね、でも、自分の意志でできることがあればやっておきたいと思いませんか。
ちょっときついですが自分の「棺桶リスト」考えてみませんか。それが、いつまであるか解らない自分の時間を更に光り輝く
ものとするのではないでしょうか。即ち、このリストは「死」のためではなく「生」のためだという事です。
でも、かような事は、あまり深刻にならず、悲壮感を持たずに、ちょっと語弊がありますが、少しユーモアをもってやってみま
しょう。
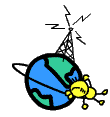
Sadahharma mail from HOUZENJI
NO95 2008.12.18
今年も師走中旬となり、一年を振り返ると世情は相変わらず混迷の呈。自然界も人間界も狂乱し、心貧しき、心迷うが故の、人
を信ずることの出来ぬが故の犯罪、不況下の政治迷走等々。。如何に苦しきことの多かりしがこの人生娑婆といいながら、絶句
する時の多い一年でした。こんな中で日蓮宗新聞「一口説法」にドキッとする記事があったので下記にご紹介します。
----------
日常、温厚で人と争うことなどない、一見非の打ち所のない人物で、その実、自分にしか関心を向けていない人。批判がましい
ことを云わず、相手を気遣う優しさで身を包む。波風立てず和を大切にする。立派、誠実と誰もが認める人。でも心の奥底では
、他人に配慮しているように見せ、和やかな振る舞う自分にしか関心がない。昨今このような人を「良心的エゴイスト」と云うの
だそうだ。
これは声聞ショウモン・縁覚エンガクの特性そのものだろう。我が国は声聞・縁覚があふれる国ではないか。夫婦や親子でさえ本音
を出さず、和やかな関係を築くことに汲々とし、僧侶も相手に配慮してみせる自分に関心があるだけ。そんなことはないだろうか。
声聞・縁覚的優しさでは、本当の人間関係は築けない。煩わしいエネルギーが必要でも、本気で相手を気にかけた関係を結ぶ、
そんな菩薩のあふれる国に脱皮したい。
-----------
上記の筆者は小生の一年後輩であるが、何かしら自分の側面を指摘されたような気がして心が穏やかならざるものを感じた
次第。上記の声聞・縁覚とは仏教の世界観の一つ十界中の存在で、共に聖者の域にあるものだが、他のための意識より自己
意識の方が強い位。これに対して菩薩とは、自己の悟りを求めると共に他への慈悲心を持つより高い立場です。
自分を顧みても、自己の本心を見せずに、他には良い坊さんを装っているのではないか。積極的には何も動こうとせずに、した
り顔をしているのではないか。。。チクチクと心に刺さる物があり忸怩たる思いと共に、辛く顔を上げることに躊躇を覚える。しかし
、一年の終わりにかくの如きの思いを自覚する事ができたという事は幸いであったのかも知れない。
大乗仏教は「人みんな菩薩なり」と説いている。でも一日中菩薩の心で過ごすことは我々凡人には至難。地獄や餓鬼・畜生の
ような心、そして声聞や縁覚の心の時間もありましょう。でも少しでも多く、心から他のために尽くす菩薩の時間が多くなるよう
に精進したいものです。
***********************************
今年のメルマガもこれが最終号となります。一年の間、勝手なことを書き連ねましたが呼んで頂いたことに感謝いたします。
12/16読売新聞の編集手帳に「1年という時間は夜汽車の旅ににている。闇が深いほど、山間に一つ、また一つと流れる灯の
色は忘れがたい」とありました。この灯は闇と対句すれば幸福の明るい色でしょうが、今年は忘れがたい辛く悲しい色が多かっ
たことでしょう。来る歳は忘れがたい幸せの色の多い年である事を祈りたいと思います。よき年の瀬と新年をお迎え下さい。

Sadahharma mail from HOUZENJI
NO96 2009.2.11
新年おめでとうも過ぎ、寒中お見舞いも、立春も過ぎて如月も中旬になります。今年も折々に種々雑感を含めて発信いたしますので、ご愛読下されば幸いです。師走に2回ほどわずかに白くなりましたが暖冬もようで楽ではありますが、これでよいのかとも心配もあります。寺の池は年末から渇水で湧水はゼロ、昨年同様に数日前から水道水にて注水(日に2時間程度)、いつもは晩霞ゼリの緑がきれいで、また、旨いのですが残念至極。速く湧き水の復活を祈る次第。。。
----------------------------------------------
少にして学べば壮にして為す/
壮にして学べば老いて衰えず/
老にして学べば死して朽ちず/
新聞に上記の儒学者 佐藤一斉(「言志四録」)のことばが掲載されていました。、いつの時でも向上向学心が必要という事でしょうが、なるほどと思えども成らぬのが現実。しかし、かく思う事ができるはこれ幸いと、へんな負け惜しみ。小生も今年は還暦となり、壮の時は過ぎているのかも知れぬが、まだ壮盛んなりと人生再出発の思い、、、だけはこれ盛ん。。。リ スタートで考えることは絵画でしょうか。高校までは絵が好きで油絵一生懸命の青春でしたので、スケッチにも行きたいとか。。。本当は音楽を何かやりたいのだが、これは我が家のDNAがいつも拒絶反応を示すのでアウト。
「老にして学べば死して朽ちず」とは強烈な言葉ですが、死も来世に向けて意味あるものにできる意味でしょう。老いてもなお、向学心、興味関心の志を持ちたいものです。日蓮聖人は「我が門家は、夜は眠りを絶ち、昼は暇を止めて之を案ぜよ。一生空しく過ごして萬歳悔ゆることなかれ」(富木殿御書)と激烈な檄を我々にとばしています。なかなかこの遺訓のようにはゆきませんが「之を案ぜよ」だけは常に心したいと思います。
ところで「壮にして学べば」ですが、過日ホームページにアップした「近代日蓮宗の思想統制」もこの一端と自画自賛です。学生時代に梵語やチベット語も含めてけっこう勉強はした方でしたので、少し仏教学をやろうと思ったのですが、語学は完全に錆び付き使い物にならず(友人に譲った辞書も多くて)、さてと思った時、以前にオヤッと思った日蓮宗の近代思想統制。再出発の第一号、かなりマニアックな方面ですがご覧下さい。
http://www.ueda.ne.jp/~houzenji/sub47.html
----------------------------------------------
お寺の新聞「法善寺だより」146号発送いたしましたのでご覧下さい。ご希望方へはどなたにでも発送いたしますので御一報下さい。紙面に寄稿等も歓迎します。

Sadahharma mail from HOUZENJI
NO97 2009.4.14
このごろの春陽気で寺の桜も満開、チューリップのツボミも大きくなって、少しずつ紫陽花、紅葉、山椒などの若芽も出てきています。境内で芽吹きの遅いものは、ザクロとナツメでしょうか。以前、古老が「ザクロの芽が出ればもう霜はない」と言っていた事を思い出しています。たびたび池の事を記していますが、ようやく湧き水が復活し一安心ですが、まだ勢いはイマイチ、昨年、蓮を入れたのですが失敗。原因は日照ということでしたので、池の周囲の立木の枝を下ろす作業をしてもらっています。池に蓮を咲かすことを夢見て数年・・いつその日が来るのでしょうか。。。
4/9は小生の誕生日で60の還暦となりました。母が84で息子が60、顔を合わせて「こんな事は想像したことがなかった・・」と少々感傷的な一時。。桜はその時季になれば正直に同じ花を見せてくれますが、それを見る我々凡夫は桜を見る心持ちは一様ならず、ある年は喜々としてして、ある年は憂いを浮かべてと悲喜こもごもでしょう。去年と同じ桜ですが小生も母、妻、愚息や娘の近況を思うと盃に桜を浮かべて乾杯とはなりません。どんな家庭でも栄枯盛衰、波風は吹きまくっています。願わくばこの春の息吹が憂きたる所を吹き飛ばしてくれることを、飛ばしてくれなくとも、憂きたるに耐える心を培う風となる事を願っています。
去年の春に母は「来年の桜は見られるだろうか」と言っていましたが、何とか大丈夫のようです。しかし、老いるという実感はかく言うものかも知れません。「老いる」とは青年期には観念であり、中年では予感であり、還暦過ぎると実感となると言います。小生も老眼となり久しく、物忘れは隠しているだけて結構な頻度。老いの入り口だと思いますが、いずれは来年を予想することに自信が持てなくもなるのでしょう。老いた母を見ているとつくづくと思います。
日蓮聖人の言葉に「親は百人の子を養えども、子は一人の親を養うこと難し」とありますがしみじみとこの言葉の重さを思い、我が身の不徳を感じています。思うような孝養はなかなかできませんが、願わくは来年も母に桜の花を見せてやりたいものだと思う桜花下にての思いです。近日中に結婚式の祝辞を頼まれていますが、いずれ親となる若き夫婦に、子として、親として、いずれ来るその時に後悔なきように、この言葉ともう一つ「親に何も孝行出来なくとも、日に一度は頬笑みを見せなさい」の言葉を贈りたいと思います。
***********
4/19日曜日は願満祭の法要です。この世の願いは種々それぞれですが、謙虚な気持ちでお願いの法要に参加しましょう。ある宗教評論家が「請求書の祈りと領収書の祈り」といいました。我々のお願いは請求書の祈りが多く、あれこれと多く仏様も「おまえは欲張り」と言っているかもしれません。でも、現実はお願いすることだられでしょう。娑婆にいるかぎり凡夫には仕方ないことです。でも、時々は「ありがとうございました」と感謝の領収の祈りも大切です。少なくとも、当たり前に朝の太陽を拝める事、食事ができる事、トイレに一人で行けること、など当然とも思うことが決して当たり前の事ではなく、大きな幸福である事に気づいて感謝したいものです。
当日は学業増進の「知恵の輪」のお守りをさし上げますので、お孫さんや子供さんもお連れ下さい。

Sadahharma mail from HOUZENJI
NO98 2009.7.26
梅雨はもうとっくに明けているはずなのですが、まだ梅雨の中のような天気が続いています。福岡や山口では死者まででる集中豪雨。災害や事故、犯罪等で非業の最期を遂げた方の目に最後に写るものは何でしょうか。迫り来る土砂、濁流、車・・・想像するのも痛ましい限りです。8/3の御施餓鬼には、このような非業の最期を遂げた方々への供養も捧げたいと思っています。
御施餓鬼というと自分の先祖供養と思っている方もいますが、決してそれだけではありません。自分に関係ある家族先祖だけの供養であっては、それは利己的、心の狭い考えで仏教が最も忌む考えの一つです。法要に参加する方が、我が先祖のみでなく、見ず知らずの霊、国や宗教や人種を越えた多くの霊、更には人間のみでなく、動物も植物も命ある全ての霊に供養の心を捧げ成仏を祈る法要が御施餓鬼です。ですから、お経の最後には必ず「願わくはこの功徳をもって普く一切に及ぼし、我らと衆生と皆共に仏道を成ぜん」と言っているのです。今年は下記の日程で開催しますので、暑い時期ですがご参加下さい。
10時 受付
10時半 護持会総会
11時 法話 講師 大阪 真如寺住職 植田観樹上人
12時半 昼食
13時半 法要
講師は住職の大学時代の同期で、現在は、お話布教を坊さんに教えているお説教の先生です。同期生でも私とはだいぶ違います。。どうしてでしょうか。。例年境内は車で大変混雑します。途中でお帰りになる方は裏の文化会館に駐車して来て下さい。おそらく、途中からでは車が出られないと思いますので。それから、塔婆希望で当日の法要には欠席の方は、その旨必ずご一報下さい。ご連絡のない方の塔婆は書くことが出来ないので、後日においでになっても塔婆はできていないという事になってしまいます。ご注意下さい。
年回の塔婆を一生懸命に書いていますが、書きながら「あーこの人も今年は○回忌か」と思い、その方の面影や思い出が湧き出します。当然ですが年と共に送り出した方か増えてきます。いずれ再会した時に、土産話がたくさんできたらいいなあとも思います。でも、「おしょう人さん、上から見てたらろくな事してねえなあ」と言われたらどうしよう。。
****************************
境内の庭がいつもぬかるんで気にしていたのですが、思い切って少々補修しました(施工は加藤建設)。表面の土を除去し、締まる岩土を入れて転圧、その後に細かい砕石を入れました。工事の後にだいぶ雨が降りましたが、水たまりもなく良好でした。
でも自転車は表面の砕石が締まっていないので、少々走るのに手こずるかも知れません。それに、秋の庭掃きはしばらくの間苦労しそうです。 でも、ぬかってグチャグチャよりはいいかな。草も少しは遠慮しそうだから。。。
******************
寺報に今年のお盆巡回予定を書いてあります。見て下さいましたか?。
12日 金井・旧北御牧
13日 常田・田沢以外の和
14日 立科・望月・佐久
15日 滋野・海野
12日.13日の方は早めにお盆棚を用意して下さい。尚、新盆の方へは寺より日程をご連絡します。
***************************
エコキャップ回収運動 ペットボトルのフタの事ですが、回収してワクチンにする運動を寺でも実施していますので、寺へおいでの時などに御持参下さい。ご協力をお願いします。

Sadahharma mail from HOUZENJI
NO99 2009.8.24
残暑お見舞いです。今年もお盆には約120軒ほどの檀家のお宅を巡回訪問させて頂きました。当山では3年に1回程度のローテーションで訪問しています。3年の変化は大きなものです。嬉しい事と辛い悲しい事を比較すると、嬉しいことは比較的忘れやすいのですが、悲しく辛い事は忘れないものです。入院や病気、家族の介護、失業、家庭問題等々の辛い訴えかけが沢山ありました。お聞きするだけで何のアドバイスもできずに帰らねばならない自分が何とも情けなく、未熟を改めて自覚した今年のお盆でした。
逆境に対した時、それを跳ね返すのは、自分の力だけでなく多くの人の力や、また、神仏の見えない力(加護)によってでしょう。自分だけに頼らず、いろいろな人に相談しましょう。家庭の事はなかなか話にくいものですが、一人で悩まない事です。寺へもいろいろな方が相談においでになります。。。が。。なかなか解決の糸口は見つからないのが現実です。でも辛い時には時々心を開放しましょう。寺は守秘義務もありますので、寺での話は一切門の外へは流れません。
お経の中に「仏様が変化の人となって救いの手を差し伸べて下さる」という文章があります。変化は「へんげ」と詠みます。信仰とは心の叫びでもあり、神仏はこれを決して見捨てはしないという事です。一人で悩まずに相談する事によって、変化の人が現れるものと信じますし、あなたが変化の人となっているのかも知れません。どんな逆境の中でも一条の光明が必ずあることを信じています。
辛い時には24時間不幸だと思いがちです。でも、歩ける・話せる・食べられる・聞こえる・トイレにも行ける・家族がいる、そして寝れば朝がくる等々、当然と思っている事が当然ではなく、とても大きな幸福である事に気がつく事が転換の第一歩ではないかと思っています。信仰はこれを後押ししてくれるものです。この幸せを「心のゆとり」としてくれるものだと思います。
***************************
ドイツのソプラノ歌手エリカ・ケートさんは言語の響きや匂いに敏感であったらしい。劇団四季の浅利慶太さんが自著『時の光の中で』に紹介している。「イタリア語を歌に向く言葉・フランス語を愛を語る言葉・ドイツ語を詩を作る言葉と評した。日本語は?の問いに〈人を敬う言葉です〉と答えた」。21.8/19読売新聞「編集手帳」より取意。
以前、日本語の乱脈について記したことがありましたが、我々は日本語を〈人を敬う言葉〉として大切にすべきであると誇りと自信を持つべきだと思います。カタカナ語の氾濫、省略語、主語のない会話、時と場所をわきまえない会話等々、坊さんの社会でもかくの如きの実態があり、若者からは少々けむたがられる還暦となったせいか、最近は特に言葉に敏感になったような気がします。
********************************
境内の山林中に「大スズメバチ」の巣が見つかり、近所から通報があったので「蜂天国」の社長さんにお願いして駆除してもらいました。蜂には迷惑千番であったと思いますが、道の周辺であったので、被害があったら大変と手を打った次第。ハチさんごめんよ。。
********************************
仏教では生老病死を四苦といい、誰れしもが避けては通れぬ大きな苦しみであるととし、この苦をどのように脱却するべきかを説いています。駒ヶ根市大法寺の藤塚上人は日蓮宗新聞に、この問題について、老い・病・看護や看取り・臨終の側面より、どうにもならないこの現実をどのようにとらえて、如何に納得し、それを受容してゆくべきかを連載しています。当山では「法善寺だより」に藤塚上人の記事を改めて連載させて頂いていますが、改めて通読する時、日本人の死の受容、死生観が我々の晩年に更に光を増すために大きなものがあると思います。死を人生の完結であると思えるために、逝く人も、見送る人も、
生きている、今この時に考えておきましょう。晩年を光ある豊かなものにするために。。
小生の母も今年で84歳となります。年ごとに力が衰えて弱気になり、共にある時間が徐々に短くなるのを覚えて、上記、藤塚師の文章を改めて読み返し、考えるところがあり母に「少しづつ読んだら」とわたしました。母もそして親を看取る私も心あつくなるものがありました。皆さんにも是非通読してほしいと思いますので、ご希望の方はご一報下さい。添付にて送信します。メールでない方へは後日郵送したいと思っています。
************************
エコキャップ回収運動 ペットボトルのフタの事ですが、回収してワクチンにする運動を寺でも実施していますので、寺へおいでの時などに御持参下さい。ご協力をお願いします。過日3回目を(約2400個)送りました。

Sadahharma mail from HOUZENJI
NO 100NO100 2009.9.12
このメルマガも100号となりました。平成9年より発信しいますが、「イターネットの時代になったが、寺も何とかこの手段を通じて、寺と皆さんと交流ができないだろうか」と思ったのが始まりでした。種々雑多に思いつくままに、特に脈絡もなく続けてきましたが、交流の一助になっているでしょうか。自己満足的採点では70点ですが。。。?大甘かな?今後も折々に、気まぐれに発信していきますが、迷惑と思わずご覧下さい。
**************
9/6今日は地元常田区の運動会で久しぶりに参加して、少々汗をかいて来ました。正直なところ、支区長なので半分義務、半分は義理の参加でしたが、いろいろな方とお会いできて参加の意義がありました。25年ぶりの綱引きや騎馬戦で少々年甲斐もなく熱くなりましたが、思ったほど疲れず、、、、まだ捨てたものでない。。。。でも、準備した多くの方の御苦労には本当に感謝します。
久しぶりのラジオ体操。大きく胸を開いて上を見ると。。きれいな青空。。。「こんな大きな青空を見るのは何年ぶりだろうか」「いつも目先のことや足許ににこだわって、深呼吸して空を見たことはなかった」と瞬間に思いました。できたならば、その場で「ワーー」と叫びたい気持ちになり、「そうだ。空は希望の青だ」「顔を上げて生きよう」と改めて感じました。今年の運動会は小生にとって還暦のワンポイントでした。
************************
同じ檀家信徒の方でも政治的信条や考え方は当然異なるものです。ですから、このメルマガでもそれを意識して、敢えて政治的問題には触れないできましたが、今回の選挙の「大勝ち」「大負け」について、また選挙制度については少々考えるべきものがあると思っていました。そんな時、檀家の峯村さんからのメルマガに、選挙制度について興味深い提案がありましたので下記にご紹介します。考えてみましょう。
極めて簡素で、民意を完全に反映できる、以下の選挙制度を提案します。
1.原則として全県一区とし、住民50万人当たり1名の議員を選出する。ただし住
民50万人以下の県でも最低1議席は確保する。
2.同一県内で5議席を超える場合は3~5議席で、なるべく少なく区割りする。
3.選挙カーを全面禁止し、テレビの政見放送と公開討論番組を運動の中心とする。
50万という数字は、議員総数を何人にするかによって適宜加減すべきです。
「有権者」でなく「住民」としているのは、子供の多い地域を有利にする配慮です。
つまり未来を背負う子供の票を、有権者である親が付託されていると考えます。なお外国人の参政権については未検討です。
この案で「1票の格差」はほとんど解消しますが、逆に人口過疎地にとって発言力が低下する憂いもあるので、過疎地の「下駄履き」として、「面積加算」などの特典で補正することも必要かもしれません。
******************************
エコキャップ回収運動 ペットボトルのフタの事ですが、回収してワクチンにする運動を寺でも実施していますので、寺へおいでの時などに御持参下さい。ご協力をお願いします。
**************************
法善寺だより151号発送しました。が。。日付の8/12は9/12の間違いです。実は8月に発行する予定で原稿を作っていたので、日付までの確認が疎かになってしまい申し訳ありません。還暦だと空元気をだしていますが、少々注意力散漫で忸怩たる思いです。

Sadahharma mail from HOUZENJI
NO101 2009.10.27
9月の中旬に上田市のKさんから「主人が亡くなりました」との電話がありました。ハテ?上田市にKさんという檀家さんはいないので、電話口で少々間が空きましたが、わかりました。Kさんは小生の高校時代の恩師の先生なのです。「エ!先生が!」と絶句しましたが、この後の電話からの声に驚愕しました。「葬儀をしてもらえないだろうか」という事なのです。「エ?ちょっと待って下さい!」と一瞬狼狽し更に間が空いてしまいました。
電話では何でも「もしもの時は清水に頼む」と先生が云っていたという事なのですが、電話では前後事情が解りませんので、とにかくすぐに伺いますと云って、急遽、先生のご自宅に急行。
高校卒業以来、一回ご自宅に伺ったことがあるのですが、年賀状の交換程度の交流でしたので、事情が全く不明、途中車の中で我が頭脳がフル回転したのですが????のままでした。ご自宅で既に物言わぬままで横たわっているK先生に、往事を思いながら枕辺のお経をあげて奥様のお話を聞きました。
「頭が痛い」といってからわずか2時間でご臨終、クモ膜下出血という事でした。「何故私に?」とお聞きすると、奥様の体調が思わしくなく、奥様がもしもの時は「清水に頼むから後は心配しないように」と先生が日頃云っていた事、去年のお盆には「清水のところへ行ってみよう」とお二人で話していた事、等々のお話があり、奥様が「主人は私のことを清水さんに託していました。ですから自分の時もきっとお願いしたと思います。だから何とかお願いします」という事でした。
なんと鈍感な私は、先生の心の奥底の声が聞こえずに今まで過ごしていたのでした。おそにく先生は何回も小生に心の中で訴えておられたのです。宗教家として忸怩たる思いとともに恥じ入るばかりでした。
不肖の教え子として、住職として、このご意志は光栄でもありますが、檀家の方でない葬儀を受ける事はすぐ「はい」と即決できるものではありません。日蓮宗法善寺としての大きな立場、地域宗教界の中の問題、本家との関わりあい等々多くの解決了解すべきことがあります。
しかし、先生の御宗旨やお寺の事、本家の事等々をお聞きし、小生がお引き受けしても問題がないことがわかりましたので、奥様のお申し出をお引き受けしました。万感の思いで先生をお送りしましたが、彷彿としてまだ20歳代後半であったであろう先生の教壇上の姿と共に、18歳高校生時代の自らの記憶が交錯し、心に熱いものがこみ上げました。そして、「いずれまたお目にかかります。。」とお別れを申し上げました。
数日後、奥様が寺においでになりましたが、玄関脇のガマズミを見て「主人はこの木がとても好きでした」そして、本堂の丸山晩霞の絵を見て「晩霞の大ファンだったのですよ」とおっしゃいました。何か不思議なつながりがあったのでしょうか。
********************************
21.10/23読売 編集手帳に下記の記事がありました。
「寺山修司の詩文集「思いださないで」のなかに、時計の一節がある。〈時計の針が/前にすすむと「時間」になります/後にすすむと「思い出」になります…〉。思えば人は、前後どちらにも針の動く時計を携えて人生を歩いている◆つらい出来事は「後にすすむ」針に託し、身は「前にすすむ」針に託す。振り向けば、耐えられそうになかった悲しみもいつしか歳月の彼方(かなた)に霞(かす)んでいる。針の動かない、壊れた時計をもつ人はどうすればいいだろう ……以下略」
時々、お通夜の席でお話しする法話の一節に「子供を失うと未来が消えるようだ。親を送ると自分の過去が消えてしまうようだ。そして配偶者を失うと現在の時が消失してしまう…」があります。連れ合いの死は、現在の時が止まったまま、時計が壊れてしまったような空白な虚脱感に陥ってしまいがちです。いや、一時的には誰でもがこんな感情を抱くのでしょう。
仏教の認識は、現実の喜怒哀楽やすべての現象を、苦であると先ず認識して、この苦の解決を思考するものです。ですから、苦を苦であると受け止めて受容しないと、解決の一歩が出てきません。でもこれは簡単なことではありません。悲しみの時間、怒りの時間や空虚な時間、人とそれぞれに必要な時間は異なりますが、涙と忍耐を背おいながら過ごす時間が、やがて諦観タイカンとなり、次の一歩へとなるのです。この諦観タイカンは一般的な「あきらめ」ではなく、苦なる事実を受容して(全ての現象は生じ滅することが大法則であることを認める事)これを乗り越え、自らの時間を築いてゆく事でしょう。これを仏教では苦ク・集ジュウ・滅メツ・道ドウの四諦シタイと言います。関心のある方は「四諦」をネット検索してみて下さい。
少々理屈っぽくなりましたが、これは原則的理論であり、我々凡人は感情に流されて、なかなかこのような心境にはなりません。しかし、悲嘆逆境の中でもこれが頭の片隅にあれば、前向きに生きる事のバネになるものと信じています。
以下の言葉は日蓮聖人の言葉です。
「ただ世間の留難来るとも、とりあへ給べからず。賢人聖人も此事はのがれず。ただ女房と酒うちのみて、南無妙法蓮華経ととなへ給へ。苦をば苦とさとり、楽をば楽とひらき、苦楽ともに思合て、南無妙法蓮華経とうちとなへゐ(唱居)させ給へ。これあに自受法楽にあらずや。」
口語的に解釈すれば「生きている限り災難というものは、聖人偉人賢人でも遭遇するものですが、それにいつまでも拘ってはなりません。もしも、そうなったら、奥さんと一杯飲んでお題目を唱えなさい。苦しみも楽しみも、どんと受け止めてお題目を唱える事が仏さまの願いなのです」とでもなるのでしょう。我々もこんな心境になりたいものです。それにしても、日蓮さんも洒落たことをおっしゃいますネ。。。。。
Sadahharma mail from HOUZENJI NO102 2009.12.19
今年も師走となりあわただしい時となりました。大晦日と元旦の一日で、世の中も自分の心も大きな変化がないことは解りきっていますが、人間には心の区切りが必要であるようです。不況の現実下で金銭の整理をしておく事はなかなか困難な場合もあることでしょう。部屋の片づけ、家の掃除、不要品の整理等々、何も年末にする必要はさらさらないのですが、それらの作業をしながら、いちいち手の取りながら、この一年の出来事を回顧し、心の中に大きな区切りをつけて、来る歳に期待と望み大きなステップとしたいものです。
日蓮聖人の言葉に「只 南無妙法蓮華経とだにも唱へ奉らば、滅せぬ罪や有べき、来らぬ福や有べき。真実也。甚深也。是を信受すべし」(聖愚問答鈔 下)があります。口語に訳せば「人生どんな災難があっても、罪として反省すべき事が沢山あっても、南無妙法蓮華経のお題目を唱え、お題目に誓い懺悔すれば、その罪は必ず許されます。また、今どんなに困窮し辛くとも、お題目により必ずや幸福がやってきます。これは深い真実です。疑うことなくこれを信じなさい」とでもなるのでしょうか。年の瀬にこのお言葉を噛みしめて今を乗り切りたいと思います。
***********************************
今年の10月に元世話人のTさんの葬儀がありました。Tさんは96歳での旅立ちでしたが、信仰心の厚い篤信の方で、曲がったことは大嫌いな実直の方でした。90歳頃までは折々に寺においでになり、信仰の話や若かかりし頃の話(武勇伝?)を語ってくれました。日頃から「俺にはお題目があるから、どんな困難や苦しみにも絶対に負けない!」と語り、筋金入りの信心家でした。そんなTさんの娘さんから電話がありました。「おじいさんがもうだめかもしれません。全身にガンが転移して回復は望めないそうです」「まだ意識ははっきりしています。法華経が支えであったおじいさんですので、会ってやってくれませなか」との事でした。
昨年、奥さんを送りましたが、気丈夫の様子でしたので驚きましたが 、やはり高齢のためかと思い、電話の思いに応えるべく、2時間後に病院へ駆けつけました。曇った寒い日でした。病室に入りましたが、Tさんは瞑目していました。声を掛けると「おー来てくれたのかい」とはっきりした声で答えてくれました。手を握り「どーしたの、調子悪いって言うからきてみたよ」と言うと、私の手が冷たかったのでしょう。「冷たくて気持ちいいよ」と、手を握りながら、まだ私が小僧で若かった頃の話しをして、いろいろ教えてもらった事を感謝しました。
しばらく病室にいました「またやっかいになるが宜しく頼む」「今の俺には怖いものはない」とはっきりと聞こえたのが印象的でした。本人も自分の病気のことは覚っていたようです。退出の時「Tさん、やっかいになったねー。また、違う世界でお会いできますね」と言ってお別れしました。これが今生の別れと私も心が熱くなっていました。この時T さんはベットの中できちんと合掌をしていました。私も南無妙法蓮華経と合掌し、私のお数珠をT さんの手にわたしました。
その5日後、Tさんは旅立ちました。篤信で精神的に強固な方でしたが、私はTさんの苦しみや悩みも知っていました。しかしTさんはそれを一言半句も私には訴えませんでした。若き日、大陸での戦争体験と自己の罪意識、長男を先に亡くした悲哀、家庭の中での信仰の対立等々。それもこれも全てお題目が支えてくれて「俺にはお題目があるから、どんな困難や苦しみにも絶対に負けない!」という自信になったのだと思いました。
「あんなに信仰していたのにTさんは不幸続きだ」という人もいました。でも、そうでしょうか。私にはTさんには大きな仏さまの御利益があったと思います。それは、誰しもが望むものですが、誰しもが得ることができるとは限らないものです。第一は96歳まで健康で長生きできた事、第二はその最後まで意識をしっかりと持ち得た事です。これは「臨終正念」リンジュウショウネンという願いです。Tさんには確実に仏さまの大きな御利益があったのです。
現在のの種々な苦しみや悩みから解放されたい、誰しもが思うところです。そして、誰しもがそれを仏天に願います。仏天の声は「足許を見よ!」「解決の一条の光は必ずある」。つまり、「泥にまみれても光を信じて精進しなさい」という声だと思うのです。ところが、長寿(長命とはちょっと違います)と臨終正念は、自己の精進では叶い難いものです。Tさんは、この叶い難い御利益を頂戴できたのだと思うのです。
お通夜の席に親戚の方が、「おじいさんの部屋に臨終正念と墨書してあったのですが、なんの意味ですか」と私に問いかけました。それは、人生の幕引き時に、我が心が乱れず平安で、我が身を次の世に自然にお任せできる事と説明をしながら、「さすがはTさん、あっぱれ」と思いました。そして、改めて目に見えぬ信仰の力に感動と力強さを感じた次第です。
********************************
寺報に載せたところですが、今年10月、日蓮宗勧学院の「嗣学」シガクの位を頂きました。日蓮宗では僧侶の位を僧階といいますが、学問の立場を勧学院カンガクインと称して、上から勧学、講学、嗣学、研学、研学補の5段階の位置があります。この嗣学に認定されたという事です。今春、この勧学のトップからこんな手紙が来ました。「最近、若い者が仏教研究に対しての情熱が薄くて困る。宗教の根幹は学問と修業だが、学的な衰退は宗門の衰退であり大いに憂慮すべきだ。多生の年寄りもこの際、後輩の刺激のためにも頑張って論文を出しなさい」
既に還暦となり、現役の仏教研究者でもないので固辞したのですが、度々のおすすめに昔の論文(印度仏教学)を提出したところ、「日蓮宗的なものを少し書きなさい」と指示がありました。さーて、今頃から落ち着いて宗門的なものを書くことは至難。そして、寺のこと、県の日蓮宗の役職、おまけに母と妻が病気がち等々で、追加論文の提出は不可能ですので辞退したいと申し出ました。ところが、、くだんのトップから電話がありました。「理由はよく解る、だがここは年寄りの言うことを聞きなさい!!」。。。こう言われると何とも抵抗できずに「はい、何とかします」と返答するのみで、この後、悪戦苦闘で30枚程度の物を書き上げて提出したような訳です。
欲しくて請求したわけではないのですが、思えば大学卒業後5年も勉強させてくれた父や、お世話になった多くの先生方への、万分の一の恩返しになればとも思って、有り難く嗣学の認定を頂戴しました。日蓮宗以外の学問を中心にやってきたのですが、これを機会に還暦の再スタートとして、もう一度、何か学問的研究に目を向けて見ようと思っています。でも、、、、、もう論文なんて書くことはないと思ったので、語学の辞書等だいぶ譲ってしまった、、、、。どうしよう。。
日蓮宗の僧侶は全国で約8300名いますが、この学階を持っているのは約35名。長野県では小生1名です。こう書くと何だか得意げですが、(寺報にはこのことは書きませんでした)また何か荷物を背負ってしまったような気持ちの方が強いのです。
*****************************
今年のメルマガもこれが最終となりました。悲喜苦楽・興亡浮沈は人の世の常ではありますが、禍福は縄の如し。今年はどうもーねー、という方も「来らぬ福や有べき」ですので明年(明るい年と書きますね)を信じて、佳き年の瀬をお迎え下さい。

Sadahharma mail from HOUZENJI
NO103 2010.1.14
今年の正月も早くも半月となり、「おめでとう」から「寒中お見舞い」となりました。今年もまた、折々に情報や雑感を勝手に発信してまいりますがご覧下さるようお願い致します。5日の読売新聞「気流」の蘭に「初めて数えてみた 母にあと何度会う」という投稿がありました。36歳の女性のものでしたが、一寸こころが熱くなりましたのでご紹介します。
----------------
一年以上前の事ですが、「あと何回、お母さんに会えるか、数えたことある?」と職場の先輩だった女性に言われました。母の家まで電車で40分ですが、私が母の顔を見るのは年に数回です。その時、70歳の母が85歳まで生きるとして、2ヶ月に1回のペースなら、会えるのはあと90回で、その少なさに驚いたものです。先輩はお母様が80歳代ということもあり「そんなに会えるの。いいわね」と涙されていました。
その後、私は育児などに追われて母とはなかなか会えずにいましたが、先日、母は持病の心臓病が悪化し、手術をしなければ、余命4.5年と宣告されたのです。まだ何百回も母に会いたい。手術の無事を祈りながら、これからは毎週会いに行くつもりです。
----------------------
あと何回、親に顔を見ることができるだろうか?通常はそんな事を考えたことはないと思いますが、確実にその日数は減ってきているのです。希にはその逆もあるのではありますが。。。会いたいと思っても、その家の事情ややっかいな人間関係等のために、会えないことも多々あることでしょう。親の命終の時を予想することなどは、とんでもない親不孝ですが、「親孝行したい時には親はなし」とならぬためには、それを考えて、自分を育んでくれた我が親とあと幾度会えるのか、あと何回話せるのかと考えてみることも大切ではないかと思います。
現実にはめったに会えなくとも、電話でも手紙でも、昨今はメールという事も可能でしょう。高齢者は寂しがりやです。そして、自分も又いずれ命があれば少々ガンコで寂しがりやの高齢者になるのです。時間を考えることは、現実性の乏しいものですが、「あと何回?」と思うと具体性がでてきます。親が存命の方はどうかお考え下さい。既に泉下に旅立ったいる方もお仏壇の前でお会いできるのですから、合掌して今日一日のことをお話下さい。 ******************************
1月17日(日)午前10時半より、お寺の新年会を行います。新年の祈願法要のあと庫裡にて昼食を兼ねて新年懇親会となります。今年一年の平安と、辛苦が来たっても、それに負けない力を授けて下さるように仏天に祈りたいと思います。日曜といえどもご多忙中、また寒い時ではありますが、ご参加下さるようご案内申し上げます。
尚、一家で何人御参加でもかまいません。また、当山の檀家以外の方の参加も歓迎しますのでお誘いあってご参詣下さい。今年も丸山さんが作ってくれた、写真入りの寺のカレンダーをさし上げます。

Sadahharma mail from HOUZENJI
NO104 2010.4.5
前号は1月でしたが既に今年も4月、ようやく春めいてきました。水仙や梅も日当たりのよい場所では花が見られますが、桜はまだで例年通り中旬の開花のようです。小生の母も今年は85才となりますが、足腰の衰えが年々目立ち散歩も思うようになりません。去年までは春暖を待つ気持ちが、それほど強くはありませんでしたが、今年は母のために一日でも早く温かく、そして桜の花が咲くことを強く願っています。
これからは新緑、希望の季節。。今年もこの春を迎えることができた事を幸いを感謝して一日一日を大切に過ごしたいものです。6日は先代の17回忌の命日となります。16年の間、先代の遺してくれた無形の財産を守ることができたであろうか。足跡を汚さずに更に寺を興隆させたであろうか。無言の遺言を守り実行できたであろうか。。忸怩たる思いの毎日ですがが、兎に角も今ここに在ることを感謝して、6日には報恩のお詣りをし、そろそろ春の味覚も味わうことができますので、、てテンプラを揚げて供養したいと思っています。蕗の薹の時期は過ぎてしまいましたが、セリやワサビの葉・・・もう少しすればウドも美味しいのです。
********************
読売新聞3月23日付 編集手帳の記事に一寸関心のあるものがありました。以下に引用します。
江戸の浮世絵師、歌川豊春に辞世の一首がある。〈死んで行く地獄の沙汰(さた)はともかくも跡の始末は金次第かな〉。心にかかる「跡の始末」とは残していく借財か、あるいは葬儀のことか
◆作者未詳の歌もある。〈死んだとて知らせてやれば来にゃならぬ つい忘れたとうっちゃっておけ〉。二首の歌を引くまでもなく、葬儀を営む側には、費用の心配と、参列者をわずらわせる申し訳なさとがつきまとう
◆宗教学者、島田裕巳氏の『葬式は、要らない』(幻冬舎新書)が売れているという。送る身、送られる身、思案する人が多いのだろう
◆洋画家の梅原龍三郎は〈葬式無用 生者は死者の為(ため)にわずらわされるべからず〉と遺言状に記した。幾度か肉親を送った経験を顧みて、悲しみのあとに用意された葬儀という非日常の“異空間”に救われた気がしないでもない。日常のなかで真向かう喪失感はたぶんもっとつらかったろう。画伯の言葉に半分うなずき、半分うなずけずにいる
◆香華を供えつつ、送られた人の声も聴いてみたいところだが、いつものことで、何も答えてはくれない。春の彼岸も、あすで明ける。
---------------
昨今の寺離れ・墓離れ・葬儀離れ、いわゆる三離れのことは些か承知していることで、寺の持っている宗教的・情緒的・知的等々の求心力低下は、寺としての存在価値の低下と等しい。寺は何のためにあるのか?誰のための存在か?。宗教とは心の安心(仏教的にはアンジンと読みます)を求めるもので、そのソフトとハードが一体化しているのが寺であり、上記の“異空間”の持つ役目であろうと思う。最近、寺としての公益性が論ぜられているが、法的専門的解釈は別にしても、ソフトとハードが機能していれば問題はクリアーできるのであろうと思う。
しかし、寺の求心力低下は現実として存在するもので、我が寺はどうであろうか?。公益性の問題も含めて、やりたい事とできる事の相克の狭間で葛藤しているのが現状。。法要等仏事は、境内環境は、敷居が高いか、住職の態度は、お布施の問題は、社会に対してのアピールは。。。総じて存在価値の有無は。。。自分のことは解らないのが世の常ではあるが果たして何点ほどであろうかと思う。自己採点では65点は頂戴できると思っているのですが、、、大甘でしょうか。点数とご意見をお寄せ下されば幸いです。
***********************
http://jvsc.jst.go.jp/shiryo/lifemeter/index.html
「ライフメーター」なる上記のネットサイトがあるのを新聞で知り見てみました。生年月日を入れると、生まれてから現在までの自分の経過時間、呼吸回数、エネルギー消費量、また、ハワイが日本に近づいた距離等が標示されます。ちなみに小生は昭和24年生まれですので、経過時間は534.624時間、呼吸回数は568.343.265回となりました。
数字で人生の時間を見ると以外に短いものだと感じます。しかし、その時間の中に確実に人生があるのです。辛いこと・嬉しいこと・悲喜苦楽の出来事が、その時間があったのです。そしてあと何時間があるのでしょうか。私の砂時計の遺された時間は?数字を見るとその感覚が現実味を帯びてきます。しかし悲観することはありません。いずれ砂時計の最後の一粒が落ちるのですが、それまでの時間を頂戴したものと思い、頂戴した・賜った時間を上手に大切にする事のきっかけにすればよいのではないでしょうか。自分の時間を大切にすることは、他の人の時間をも大切にすることに繋がるのではないかとおもいます。一度このサイトをみてはどうでしょうか。おすすめします。

Sadahharma mail from HOUZENJI
NO105 2010.4.27
我々は時々「永遠」「久遠」「不滅」「無限」等々の言葉を何気なく使っている。特に小生などの立場では煩雑に過ぎると言ってもよいほど、この言葉を多用している。宗教にとってこれらの言葉や意味するものの比重は非常に大きい。何故ならば、宗教的「救い」は現在のみのものではなく、過去や未来にまで及ぶものであるからであろう。日蓮宗にしても、
過去・現在・未来の三世常住の釈尊に救いの安心を求める立場であるので至極当然である。
既に30年ほど以前のこと、宇宙は有限か無限か、と研究者に尋ねた時、瞬時に「有限です」と返答されたことがあったが、甚だショックであったことを思い出す。以来、心の底に常に抱えている問題であったが、改めて考える必要性も時間もなく今に至っている。
しかし、ときどき感ずるのは「人々は宗教の説く無限・永遠を本当に信じているのだろうか」という宗教者としては甚だ青くさい幼稚で未熟な疑問である。我々の小さな命は、やがては永遠なる大きな大生命に回帰する・お返しするのだと説いている自分を、また違う自分が「本当かい」とあざ笑っているような気がしてならない。時として、この問題を科学的に追求されたら、その答えに窮して立ち往生してしまうのではないか、と不安が湧いてくる。「永遠・無限等」は哲学的・宗教的・思索的な形而上の単なる観念なのか、実証的現実的側面があるのか、時間の連続性に過ぎないのか。はたまた時間はどこからがスタートなのか。
「形ある物は必ず滅する」の法則は、生滅の無常を示し、現在の有と、必ずある滅との関係であるが、その根本には、若しくはその延長線上にあるのは「永遠」の概念である。しかし、永遠が生滅する無常の連鎖とすると、滅からの再生、無から有へと「永遠」に繋がる連鎖の鎖は発見し難い。存在する有の滅後の存在は、個人的未来観・宗教観・哲学等の観念世界に突入する問題となる。
しかし、「永遠」なるテーマは、特定の未来観・宗教観・哲学等を持つ者にとっては確実に存在し、それらを有しない〈縁なき衆生〉にとっては、人間が創出した単なる戯れ言の観念なのであろうか。
科学と宗教はどの時代にても悩ましい問題を惹起してきたが、この現代に於いては、ある程度「永遠」を説明できる事が必要ではないかと思う。
この説明に「食物連鎖」、死後生体の分子的分解→大海→蒸発→雨→植物→動物なる「生命の循環」、また現代ではDNAの未来への連続などが考えられる。いずれも永遠に救いを感ずる者にとっては納得できるものであるが、否定を前提とすれば誠に簡単に否定されてしまう。例を挙げたものは、いずれも大地(地球)の存在が前提であり、地球が終焉を迎えれば、全ての理屈は雲散霧消してしまう。
137億年前、ビックバンによってこの宇宙が発生し、膨張を続け、地球は46億年以前に誕生、そして50~70億年後には終焉を迎える事は、現代科学の常識でもある。永遠の考えはやはり宇宙的スケールで考えるべきなのかも知れない。
解答のヒントに、昨年の11/22読売新聞 連載 長寿革命 死生観5にノーベル物理学賞受賞者の小柴昌俊博士の「宇宙の神秘 壮大輪廻」なる記事があった。以下にメモすべき点を引用する。
「この宇宙に次々に生まれた巨大な恒星。それが寿命を迎えて大爆発した際、大量に放出された素粒子ニュートリノの働きで、水素からウランまで92種類の元素すべてが宇宙空間にばらまかれた。ニュートリノがなければ、46億年前に地球も生まれず、生命の誕生もなかった」「途切れることのない循環が地球全体の命を支えている。あらゆる生命は外から元素を取り入れて生き、死んで外の世界に元素を供給する」「科学は、地球に壮大な輪廻があることを証明したのです」
つまり、地球の誕生は巨大恒星の爆発による元素の集積であり、地球が消滅しても、その元素がやがて集積し物質化して新たな星を生成させるという事。滅亡と再生という「永遠」のリングが物理学から証明された事になる。しかし、この考えからは未来への連続性(永遠)は理解できるが、過去への永遠性はビッグバンまでとなるのか?。連続する時間のスタートはここからなのか?この後の問題は時空のゆがみ、曲がりの問題を含む相対性理論の範疇となり小生には荷が重すぎるので言及困難。
そもそも物理的に解釈される「永遠」と、宗教的な「永遠」とを同一線上で一致点を模索すること自体が無意味なのかも知れない。しかし、宗教が現実社会に正対している以上は、科学物理の世界に背を向けてよいという事にはならない。上記にはかなり論理の飛躍があると思うが、永遠の救いを説く宗教は、この「永遠」自体について現代人に通用する言葉で(宗教的専門用語でなく)、説明の用意が必要になってるのかも知れない。

Sadahharma mail from HOUZENJI
NO106 2010.6.27
「お上人さん。俺も年をくった。女房も先に逝って、子供もいない。病気もあんまり素性のいいものじゃなく先も見えたようだ。」「人生、紆余曲折で迷惑かけた人も多いし、世話になった人も多い。」「戒名ももらったし、ここらで世話になった人に、今、感謝のお別れ会をしたい」檀家のAさんからこんなお話があったのは今年の春でした。
ご本人は生前葬のつもりでの計画でしたが、会場予定のホテルからは生前葬の名前では困るという事で「いい日旅立ちの会」という会費制のお別れ食事会になりました。
ご本人を囲み、右に住職の小生、左に主治医のドクター。身内では甥の家族、そして友人知人20名ぐらいが集まっての食事会。冒頭に本人が生涯を回顧して、参列者に御礼の言葉と今後の覚悟を述べ、友人代表が「乾杯でいいんだな」戸惑いながらも激励を込めて乾杯。その後、幼年期からの写真からのスライドショー。酒間、本人が写真を見ながら当時を回顧し、友人もそれに応じて歓談。。心はタイムスリップしていたのでしょう。
最後に、住職としての小生に声が掛かりました。昨今の終末医療の問題などとからめて、本人の覚悟、宗教的安心アンジンについてふれ、最後に「臨終の事をおもうて他事を習うべし」の日蓮聖人言葉がいつの時代にも新しい切り口で我々に迫り、そして求めている事を述べて挨拶を終えました。
さて、参会者誰しもが思っていた事は「本番ではどうするのか」という事です。本人は「甥が看取ってくれることになっている。そして、火葬の後に墓地に入れてもらう。だから皆さんには通知はしない。そのための会だ」という事でした。しかし、小生は火葬の前には必ず行くので知らせるようにと、甥のかたにそっと伝えておきました。
最近、都会では直葬といって、病院から火葬そして埋骨と宗教的送りの葬儀をしない方法が増えていると言います。家族に迷惑をかけたくない、寺や僧侶への信頼不足、金銭的側面、また葬儀自体への不要論等々理由は様々です。しかし、葬儀は人生の完結であり卒業式でもあります。身内や社会の残った人々は「よくガンバッタね」と卒業式をしてあげたいものだと思います。どんな形にしても。 さて、あなたはどう思いますか。
『葬式は要らない』 『葬式は必要』 『お坊さんが隠すお寺の話』などの本が出版されています。面白いですよ。
*****************************
遅い梅雨いりでしたがようやく例年通りの天候となりました。 例年、梅雨の前には屋根とトヨの掃除をしていますので、2日間をかけて少しずつ屋根掃除をしました。これをさぼっていると、大雨時にトヨから雨水が逆流して雨漏りとあいなり大騒ぎなのです。家人からは「もう年なのだからやめたら」と言われますので、子供達にもやらせているのですが、性分なのでしょうか、先ず自分でやらなければ気が済まないところがあって、つい梯子を掛けて登ってしまうのです。 でも、そろそろ止めた方が無難でしょうか。滑り落ちて何とかの冷や水なんて言われないうちに。。。

Saddarma mail from HOUZENJI
No107 2010.11.16
今年も霜月中旬、境内の銀杏も半分はもう散ったでしょうか。今年は春夏の異常気象のせいか、ギンナンがほとんどなりません。おかげで庭掃除が簡単で大いに助かっていますが、何となく物足りなさもあります。思えば今までにこんな年が2、3年あったように思いますが、ほとしどの年は「モウイイヨ」というほど、足の踏み場もないほど落ちて、その臭いに閉口したものです。そろそろ拾いにくる方もいますがガッカリしています。でも、こんな事もありますよ。時には。。
****************************
前号は6月でしたのでだいぶ御無沙汰ですが、じつは2週間ほど入院して10月末に退院しました。胃が自分勝手なことを始めてしまったので、これを少々荒療治でいうことを聞かせた次第。
ということで目下のところ、食事はお粥等の比較的柔らかなものを主に5~6回、刺激物はしばらく遠慮、もちろんアルコールも。軽作業は可能ですが、つい頑張ってしまうので自重自戒の毎日。自分で何でもやらねば気が済まない性格なので、こちらのストレスとのだまし合いです。
しかし、始めての体験で病院と病気を観察してよい経験になりました。 檀家の方が入院などをすると、「24時間の中で治療中で病人でなければならない時間と、病人でない時間があるはずだから、この病人でない時間を与えられた時間として意識してみましょうよ」と言っていたのですが、これが可能なのか。実際には痛みや辛さの最中にはまず困難。出来ることは「始めがあれば終わりもある」と観念し、耐えて祈るのみでした。事実、手術翌日の夜から翌朝にかけては痛みが断続的に続いて、「悪いなあ」と思いながらナースコールを押し続けたものです。この時間が過ぎると点滴しながらでも、気分は病人から脱することができ、読書やお経を読むことが可能となりました。痛みのコントロールがいかに時間の質を左右させるかを実感しました。
時間だけは十分あるので読書もしていましたが、病気もあまり性格のよいものでないので、思い立ってバケットリストを考えました。(思ったほど深刻にならなかったので半分は冗談ですが)これは以前このメルマガでもとりあげた、ジャックニコラウスとモーガンフリーマン主演の映画の原タイトル。かなりプライベートなものになるので公開は遠慮しますが、一つは仏教セミナーできちんと法華経講義をすること。もう一つは日蓮聖人の御遺文全部を通読する事。。等々。。。
お見舞いで「少しは休みなさいという事だから、ゆっくりと静養することだよ」とよく言いますが、苦痛が一段落した入院患者に果たしてどうでしょうか。その段階では一日も早く退院したい気持ちが高まっているので「何言ってるんだ人の気持ちも知らないで」ともなりかねません。わずかな入院期間でしたが「家に帰りたいよ」という気持ちがよくわかりました。
以下は入院中に読んだ本。既に読んだ本ですが、病気となりベッドで読み返すと、第三者的思いでなく、一人称的にとらえるので別な意味合いと真剣味を感じた次第です。
『老いの才覚』 曾野綾子 『妻を看取る日』垣添忠生 『老年を幸福に生きる』中野孝次 『お釈迦様の脳科学』苫米地英人 『ながい旅』大岡昇平 『代表的日本人』内村鑑三
『インフォームド・コンセント』森岡恭彦 『武石村往診日記』矢島嶺 『看取りの心構と作法』
******************************
12/8の日は火災等の厄難を防いでくれるという信仰がある「荒神祭」コウジンサイです。既に毎年申し込みがある方にはご案内を申し上げていますが、新規ご希望の方も歓迎しますので、新規にご希望の方はご一報下さい。法要は午後2時からで法要後にお札と御幣を差し上げますので、台所等に安置してください。遠方の方には郵送もしていますので、その旨もお知らせ下さい。
********************
境内の落葉、紅葉が見事です。自然は毎年同じ風景を見せてくれます。しかし、生きている我々は、その同じ景色を去年と同じ気持ちでは見ていません。皆さんはどうですか。去年見た紅葉の時、心に思っていた事と、今年の今の心はどう違いますか。小生は一期一会というか、この景色、果たして来年も見ることができるだろうか?と真剣に思い、ちょぴり素直になりました。昨年までは「あーまた庭掃除か。。。」などと思っていたのですが。。。

Saddarma mail from Houzenji
No108 2010.12 . 14
読売 編集手帳(11/26)に下記の記事がありました。
ユーモアとは〈「にもかかわらず」笑うこと〉だという。ドイツの哲学者、アルフォンス・デーケン氏が著書に書いていた。辛いことがあり、苦しいことがあり、にもかかわらず笑うことだ、と。フランスの作家、ジュール・ルナールも〈ユーモリストとは不機嫌を上機嫌にぶちまける人のことである〉と語っているところをみれば、ユーモアとはきっと、涙や冷や汗を養分にして咲く花のようなものなのだろう。……
アルフォンス・デーケン氏は日本に死学の概念を定着させた上智大学の教授。死生学についての著書が多いが、老いとユーモアに関するものもある。「辛いことがあり、苦しいことがあり、にもかかわらず笑う」「不機嫌を上機嫌にぶちまける」は少々つらい面もあるが、そうかも知れません。小生が2週間の入院生活の中でも看護師さんのユーモアにはずいぶんと助けられた気がします。辛く不如意な体調の時など、笑顔とちょっとしたユーモアはまさに「涙や冷や汗を養分にして咲く花」のような救いがあり、そのユーモアによってこちらもユーモアを返す余裕が生まれたものでした。
しかし、頻発する凶悪犯罪や自殺(自死)、尖閣問題や北方領土の問題、北朝鮮問題等ナショナリズムを包含する問題などには、咲かせようにも咲かせることが困難なものがある。振り返って見れば最近の社会はこのようななんともやりきれない事ばかり目立つようだ。 何も大上段に振りかぶる必要はないが、一年の終わりの時、我がこの一年に潤いの花であるユーモアの心・精神を持てたであろうか、この精神は自己のためと同時に他のためでもある。さて今年の我がユーモア精神は何点であっただろうか。来年のためにもそれぞれ採点してみたいものです。
******************
12/5タイヤ交換3台全て完了、。我が家ではスタンドに依頼したことがないので一日大騒ぎですが、いよいよ冬が迫ったことを感ずるひとときです。おっと、そういえば今年4/17に雪が積もり収納した雪かきがそのまま車庫に鎮座していました。。しまい忘れです。
***************
落ち葉の処理も一段落ですが、掃除をして上を見ると葉が散りきった立木がすがすがしく美しく見える。新緑の木、花をつけた木、錦の紅葉もそれぞれの美しさがあるが、師走の立木も綺麗である。一切の飾りを拒絶してやせ細った枝だけの木々には、凛とした、そして不退転とも言える、近寄り難く厳しい威厳にも似た圧倒的な存在感がある。
そして、来る春に備えて力を蓄える。人間も興亡浮沈の存在。困難辛苦の逆境の時は虚飾を落として、風雨に耐えて体力を蓄え時を待って再起を期すのだと思う。また、青春の時、中年・熟年の壮年期を過ぎた老年期の姿を冬木立に重ねて見ることもある。誰しもに来るその時、吹雪や嵐にも耐えて尚も折れない、この時期の冬木立のような山水画の如くの美しさを持つ存在になりうるだろうか。己の晩年を思うとき白黒画のような木々の情景が問いかけているような気がする。そして、木々からの声が聞こえる…「生を生ききることだよ」と。。。
*************************
12/31大晦日・午後11時5分頃より「二年参り」のお参りをします。かつては、法要の後に祝宴をしていたのですが、車とお酒の問題もあり自粛しています。今年も喜怒哀楽の時間が交差したこの一年でありましたが、心が引き締まる如くの本堂で行く年に感謝し、来る新年を読経の中で迎えたいと思います。どうぞ充分厚着をしてお参り下さい。新年を迎える開運のお守りを差し上げます。(このお守りは大晦日のみに差し上げています)
そけではまた来春。