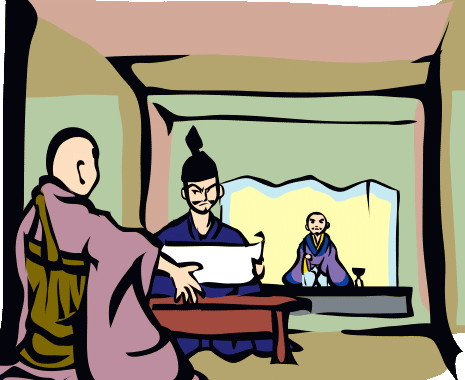
日蓮聖人の著述
| 和 暦 | 西 暦 | 聖寿 | 著 作 | 著作の相手 | 著作場所 | 『昭和定本』頁 | 『米田本』 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仁治3年 | 1242 | 21 | 『戒体即身成仏義』 | / | 清澄 | 1 | / |
| 正元元年 | 1259 | 38 | 『守護国家論』 | 鎌倉 | 89 | 4 | |
| 正元2年 (文応元年) |
1260 | 39 | 『災難興起由来来』 『災難対治抄』 『立正安国論』 |
/ / 北条時頼 |
鎌倉 / 鎌倉 |
158 163 202 |
61 67 77 |
| 弘長2年 | 1262 | 41 | 『顕謗法鈔』 『教機時国抄』 |
/ / |
伊東 / |
247 241 |
98 / |
| 弘長3年 | 1263 | 42 | 『持妙法華問答鈔』 | / | 鎌倉 | 274 | / |
| 1264 | 43 | 『南条兵衛七郎御書』 | 南条氏 | 安房 | 319 | 120 | |
| 文永3年 | 1266 | 45 | 『法華題目鈔』 『善無畏鈔』 |
/ / |
清澄 / |
391 408 |
134 146 |
| 文永5年 | 1268 | 47 | 『安国論御勘由来』 『安国論副状』 |
法鑑坊 北条時宗 |
鎌倉 鎌倉 |
421 421 |
152 151 |
| 文永6年 | 1269 | 48 | 『安国論奥書』 『法門可被申様之事』 |
/ 三位坊 |
鎌倉 / |
442 443 |
158 159 |
| 文永8年 | 1271 | 50 | 『五人土籠御書』 『寺泊御書』 『転重軽御法門』 『土籠御書』 |
日朗以下5名 富木常忍 太田乗明 筑後 |
相模依智 相模依智 相模依智 相模依智 |
507 512 507 509 |
180 184 182 / |
| 文永9年 | 1272 | 51 | 『法華浄土問答鈔』 『八宗違目鈔』 『開目抄』 『真言諸宗違目』 『祈祷抄』 『佐渡御書』 『法華浄土問答鈔』 『富木殿御返事』 『日妙聖人御書』 |
/ 富木常忍 / 富木常忍 / 弟子旦那中 / 富木常忍 乙御前母 |
佐渡塚原 佐渡塚原 佐渡塚原 佐渡一谷 佐渡一谷 佐渡塚原 佐渡塚原 佐渡一谷 佐渡一谷 |
518 525 535 638 667 610 518 619 641 |
189 193 202 266 277 / 189 265 270 |
| 文永10年 | 1273 | 52 | 『観心本尊抄』 『顕仏未来記』 『小乗大乗分別鈔』 『木絵二像開眼事』 『如説修行抄』 『妙一尼御返事』 『富木殿御返事』 『乙御前母御書』 『諸法実相鈔』 |
/ / / / / 妙一尼 富木常忍 日妙尼 最蓮房 |
佐渡一谷 佐渡一谷 佐渡一谷 佐渡一谷 佐渡一谷 佐渡一谷 佐渡一谷 佐渡一谷 佐渡一谷 |
702 738 769 791 731 722 743 754 723 |
293 316 326 334 / 315 321 324 / |
| 文永11年 | 1274 | 53 | 『法華取要抄』 『法華行者値難事』 『上野殿御返事』 『聖密坊御書』 『曽谷入道殿御書』 |
/ 富木常忍・四条金吾 南条時光母 聖密坊 曽谷教信 |
身延 佐渡一谷 身延 身延 身延 |
810 796 819 820 838 |
342 338 351 352 359 |
| 文永12年 | 1275 | 54 | 『神国王御書』 『種種御振舞御書』 『撰時抄』 『四条金吾殿女房御返事』 『可延定業御書』 『曽谷入道殿許御書』 『兄弟鈔』 『一谷入道御書』 『妙一尼御前御消息』 『大学三郎殿御書』 『太田入道殿御返事』 『妙心尼御前御返事』 |
/ / / 四条金吾妻 富木常忍妻 曽谷教信 池上宗仲・宗長 一谷入道女房 妙一尼 大学三郎 太田乗明 妙心尼 |
身延 身延 身延 身延 身延 身延 身延 身延 身延 身延 身延 身延 |
877 959 1003 855 861 895 918 989 999 1081 1115 1102 |
381 445 477 366 370 393 415 465 473 533 544 541 |
| 建治2年 | 1276 | 55 | 『報恩抄』 『清澄寺大衆中』 『松野殿御消息』 『忘持経事』 『南条殿御返事』(大橋書) 『四条金吾釈迦仏供養事』 『事理供養御書』 『光日房御書』 『富木尼御前御返事』 |
/ 清澄大衆 松野六郎左衛門 富木常忍 南条時光 四条頼基 / / 富木常忍妻 |
身延 身延 身延 身延 身延 身延 身延 身延 身延 |
1192 1132 1139 1150 1170 1182 1261 1152 1147 |
588 554 558 563 572 580 633 565 561 |
| 建治3年 | 1277 | 56 | 『四信五品抄』 『上野殿御返事』 『下山御消息』 『崇峻天皇御書』 『安国論 広本』 『法華初心成仏鈔』 |
富木常忍 南条時光 下山兵庫五郎 四条頼基 / / |
身延 身延 身延 身延 身延 身延 |
1294 1305 1312 1390 1455 1413 |
637 648 653 691 708 / |
| 弘安元年 | 1278 | 57 | 『富木入道殿御返事』 『日如御前御返事』 『千日尼御前御返事』 『妙法尼御前御返事』 『食物三徳御書』 『随自意御書』 『衣食御書』 |
富木常忍 日如御前 千日尼 妙法尼 / / / |
身延 身延 身延 身延 身延 身延 身延 |
1517 1508 1538 1535 1607 1610 2974 |
746 740 758 756 775 777 785 |
| 弘安2年 | 1279 | 58 | 『上野殿御返事』 『松野殿女房御返事』 『四条金吾御返事』 『聖人御難事』 |
南条時光 松野入道尼 四条頼基 門下人々 |
身延 身延 身延 身延 |
1621 1651 1665 1672 |
786 794 796 800 |
| 弘安3年 | 1280 | 59 | 『諫暁八幡抄』 『太田殿女房御返事』 『千日尼御返事』(阿仏坊書) 『盂蘭盆御書』 『上野殿御返事』 『上野殿母尼御前御返事』(中陰書) |
/ 太田乗明妻 千日尼 治部房祖母 南条時光 南条時光母 |
身延 身延 身延 身延 身延 身延 |
1831 1754 1759 1770 1793 1810 |
850 820 824 831 836 840 |
| 弘安4年 | 1281 | 60 | 『重須殿女房御返事』(十字書) 『上野殿母尼御前御返事』(所労書) |
石川新兵衛入道妻 南条時光母 |
身延 身延 |
1855 1896 |
871 888 |
| 弘安5年 | 1282 | 61 | 『波木井殿御書』 | 波木井実長 | 池上 | 1924 | 895 |
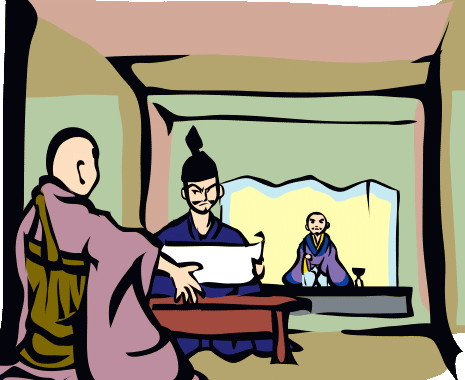
日蓮聖人が書き著された多くの著作、書簡等は、御書・祖書・御妙判・御消息などと、その形態によって呼称されるが、全体を総して「御遺文ゴイブン」と言われている。『日蓮宗事典』によれば真蹟(真筆)と確認されている著作・書状は完全な形で現存している物113、不完全な断簡87、かつての存在が確実な物25、その他、図録、要文、書写本、数文字・数行のものを含めると千以上のものになり、この数は鎌倉時代の各祖師の中では最大数となる。
御遺文の編集は日蓮聖人滅後100年頃から『録内御書』『録外御書』が作られ、以来、種々な御遺文集が編纂されてきた。近世に至り明治13年(1880)小川泰堂の『高祖遺文録』、明治37年(1904)これを修補校正した『日蓮聖人御遺文』(縮刷遺文)、昭和27年(1852)さらにこれを底本として『昭和定本日蓮聖人遺文』(昭和定本)4巻が刊行された。
真蹟(真筆)の編纂は大正3年及び昭和27年に『日蓮聖人御真蹟』が刊行、昭和51年に『日蓮聖人御真蹟集成』10巻が法蔵館より公刊されている。
近世より様々な見地立場から、諸師が御遺文の編集や整理をされてきたが、最近年のものとして、米田淳雄師が平成6年に約230点の主要遺文を編纂した『平成新修日蓮聖人遺文集がある。』
下記の表は本ホームページ管理者が個人的学習のための視点で選んだものを『昭和定本』正篇(1.2巻)より整理したものである。尚、閲覧に便利な米田師の『平成新修日蓮聖人遺文集』を『米田本』としてその頁を示した。
同一年の著作の順序は必ずしも著作月日順ではない。
日蓮聖人の三大部・五大部
『立正安国論』『開目抄』『観心本尊抄』を三大部、これに『撰時抄』『報恩抄』を加えて五大部と称する。
『開目抄』
ご真蹟は身延山にあったが明治8年1月10日の大火により焼失、写本等によりかつての存在が明確である、これを 「曾存」と称している。
著作の理由 A.日蓮聖人の生涯は迫害受難の連続であったため、弟子や信徒の中から退転する者が続出したために、布教と迫害に対する弟子達の疑問を払拭するため。 B.末法の導師が日蓮自身であることを明確にするため。 C.佐渡の流刑地にあって死を覚悟した日蓮聖人が弟子達に「かたみ」として残すため。
「...孝と申すは高きなり。天、高けれども孝よりは高からず。また、孝とは厚きなり。地、厚けれども孝よりは厚からず。聖賢の二類は孝の家よりいでたり。いかに況や、仏法を学せん人、知恩報恩なかるべしや。..」米209
「..儒家の孝養は今生に限る。未来の父母を扶けざれば、外家の聖賢は有名無実なり。外道は過未をしれども父母を扶る道なし。仏道こそ父母の後世を扶くれば聖賢の名はあるべけれ。しかれども、法華経已前等の大小乗の経宗は自身の得道なおかないがたし、何に況や父母をや。ただ、文のみあって義なし。今、法華経の時こそ、女人成仏の時、悲母の成仏も顕はれ、達多の悪人成仏の時、慈父の成仏も顕はるれ。この経は内典の孝経なり..」 米247
「..我れ日本の柱とならん、我れ日本の眼目とならん、我れ日本の大船とならん 等のちかいやぶるべからず..」
米258
「..天の加護なき事を疑はざれ、現世の安穏ならざる事をなげかざれ..」 定604 米260
『報恩抄』 真蹟は身延曾存。
清澄のかつての師い゛ある道善房遷化を知り、旧師の追善のため執筆されたもの。人として行うべき根本を「知恩報恩」とし、法華経信仰の実践が真実の報恩であると説いている。
「それ老狐は塚をあとにせず、白亀は毛宝が恩を報ず。畜生すらかくのごとし。いわんや人倫をや。..」 定1192 米588
「..日蓮が慈悲広大ならば、南無妙法蓮華経は萬年の外、未来までもながるべし。日本国の一切衆生の盲目をひらける功徳あり。無間地獄の道をふさぎぬ。この功徳は伝教天台にも超え、龍樹・迦葉にも優れたり。極楽百年の修行は穢土一日の功に及ばす。正像二千年の弘通は末法の一時に劣るか。是れひとえに日蓮が智の賢きには非ず。時のしからしむるのみ。春は花さき、秋は菓なる、夏はあたたかに、冬は冷たし。時のしからしむるに有らざるや..」
「..されば花は根にかえり、真味は土にとどまる。..」 米632
『観心本尊抄』 真蹟は中山法華経寺。
正式な名称は『如来滅後五五百歳始観心本尊抄』と言う。末法衆生救済の大法を示した書。救済の道を天台の一念三千から日蓮聖人の事の一念三千に導き、南無妙法蓮華経のお題目の受持へと導いている。本抄の説によって最初の大曼陀羅が佐渡にて描かれた。これを「佐渡始顕の大曼陀羅」と称する。
「..釈尊の因行果徳の二法は妙法蓮華経の五字に具足す。我らこの五字を受持すれば、自然に彼の因果の功徳を譲り与えたもう..」
「..今、本時の娑婆世界は三災を離れ四劫を出たる常住の浄土なり。仏すでに過去にも滅っせず未来にも生ぜず。所化もって同体なり。これ即ち己心の三千具足三種の世間なり。..」
「..天晴れぬれば地明らかなり。法華を識る者は世法を得べきか。一念三千を識らざる者には仏大慈悲を起こし、五字の内にこの珠をつつみ、末代幼稚の頸に懸けさしめたまう。..」
『法華初心成仏鈔』
「..我が己心の妙法蓮華経を本尊とあがめ奉りて、我が己心の仏性 南無妙法蓮華経と呼び呼ばれて顕れたもうところを仏とは云うなり。たとえば籠の中の鳥なけば空とぶ鳥の呼ばれて集まるが如し。空とぶ鳥の集まれば籠の中の鳥も出んとするが如し。口に妙法をよび奉れば、我が身の仏性も呼ばれて必ず顕れたもう。..」
『諸法実相鈔』
日蓮教学の重要な観念・思想である「諸法実相」についての解釈が詳細になされている書。即ち、諸法実相とは妙法蓮華経の五字であり、それは寿量品の一念三千の法門である事を説く。
「.実相と云うは妙法蓮華経の異名也。諸法は妙法蓮華経と云う事也。地獄は地獄の姿を見たるが実の相なり。餓鬼と変ぜば地獄の実のすがたに非ず。仏は仏のすがた、凡夫は凡夫のすがた、萬法の当体の姿が妙法蓮華経の当体なりと云う事を諸法実相とは申すなり。..」
「..現在の大難を思いつづくるにも涙、未来の成仏を思うて喜ぶにも涙せきあへず。鳥と虫とはなけども涙落ちず。日蓮は泣かねども涙ひまなし。此の涙 世間の事には非ず。ただひとえに法華経の故なり。もししからば甘露の涙とも云うべし..」
「..末法にして妙法華経の五字を弘めん者は男女をきらふべからず、皆地涌の菩薩の出現に非ずにば唱え難き題目なり..」
定726
『崇峻天皇御書』 真蹟身延曾存
崇峻天皇に関する記述があるのでこの名称があるが、「同地獄鈔」とも云う。
「..人身は受けがたし爪の上の土。人身は持ちがたし草の上の露..」 米695
「..あなかしこ あなかしこ。蔵の財タカラよりも身の財タカラすぐれたり。身の財タカラより心の財タカラ第一なり。この御文をご覧あらんよりは心の財をつませ給うべし..」 米695
「..一代の肝心は法華経、法華経の修行の肝心は不軽品にて候なり。不軽菩薩の人を敬いしは如何なる事ぞ。教主釈尊の出世の本懐は人の振る舞いにて候けるぞ。あなかしこ あなかしこ 賢ききを人と云い、はかなきを畜という。」 米696
『千日尼御返事』 真蹟 佐渡妙宣寺
千日尼とは佐渡の阿仏房(遠藤為盛)の妻で、夫共に日蓮聖人の弟子となって聖人に仕えた。この返書は阿仏房追善のもので「阿仏房書」ともいう。
「..男は柱の如し、女は川の如し。男は足の如し、女は身の如し。男は羽の如し、女は身の如し。羽と身とべちべちなりなば、何をもってか飛ぶべき。..」 米826
「..散りし花もまた咲きぬ。落ちし菓コノミもまたならぬ。春の風もかわらず。秋の景色もこぞの如し。いかにこの一事のみ変わりゆきて本のごとくなからむ。..」 米827
『土籠御書』
日蓮聖人が相模依智より佐渡配流地へ出発前夜10月9日に、鎌倉の土牢に幽閉されている日朗上人に与えたもの。
「日蓮は明日 佐渡の国へまいるなり。今夜の寒きにつけても、牢の内のありさま、思いやられていたわしくこそ候へ。あはれ殿は法華経一部を色心二法共にあそばしたる御身なれば、父母六親一切衆生をも助け給べき御身なり。法華経を余人の読み候は口ばかり言葉ばかりは読めども心は読まず。心は読めども身に読まず。色心二法共にあそばされたること貴く候へ。..」
『重須殿女房御返事』 真蹟 富士大石寺
供物に対する礼状で、己心に仏と地獄ともに在ることを説く。
「..地獄と仏とはいずれの所に候ぞとたずね候へば、或いは地の下と申す経もあり、或いは西方等と申す経も候。しかれども委細に尋ね候へば、我らが五尺の身の内に候とみへて候。さもや おぼえ候ことは、我らが心の内に父をあながり、母をおろかにする人は、地獄其の人の心の内に候。例えば、蓮の種の中に花と菓と見ゆるが如し。仏と申す事も我らの心の内にをわします。..」 米871
「..蓮はきよきもの、泥よりいでたり。栴檀はこうばしき物、大地よいでたり..」 米871
「..月は山よりいでて山を照らす。わざわいは口よりい出て身をやぶる。幸いは心よりいでて我をかざる..」 米871
『事理供養御書』 真蹟 富士大石寺
「観心の法門」を具体的な事例をあげて説いている。
「..命と申す物は一切の財タカラの中に第一なり。遍満三千界無有直身命と説かれて、三千大千世界にみてて候財も命にはかへられぬ事に候なり。されば命は灯火のごとし。食は油のごとし。..」 米633
「..財なき人々もあり。財あるも財なきも、命とむ申す財にすぎて候財は候はず。..」 米633
「..爾前の経々の心は、心より万法を生ず。例えば心は大地の如し、草木は万法の如しと申す。法華経はしからず。心すなはち大地、大地すなはち草木なり。爾前の経々の心は 心の澄むは月の如し、心の清きは花のの如し。法華経はしからず。月こそ心よ 花こそ心よと申す法門なり。..」 米634
『妙一尼御前御消息』 真蹟 中山法華経寺
妙一尼を日昭の母とする説があるが詳細は不明。この書状は法華経を信奉した亡夫の成仏を説き、尼を慰めるためのもの。
「..法華経を信ずる人は冬のごとし、冬は必ず春となる。いまだ昔より聞かず、見ず、冬の秋とかへれる事を。いまだ聞かず、法華経を信ずる人の凡夫なる事を。..」 米475
『忘持経事』 真蹟 中山法華経寺
富木常忍が亡母の遺骨を供養のために身延に持参したが、帰りに自らの持経を忘れ帰ったので、その持経を送り届けた時の書簡。孝養を讃え、亡母の成仏を願っている。
「..教主釈尊の御宝前に母の骨を安置し、五体を地に投げ掌を合わせ、両眼を開きて尊容を拝するに、歓喜身に余り心の苦しみ忽ちに息む。我が頭は父母の頭、我が足は父母の足、我が十指は父母の十指、我が口は父母の口なり。例えば、種子タネと菓子コノミと身と影の如し。..」 米564
『光日房御書』 身延曾存
安房の光日尼の子供「弥四郎」死去への弔意と教えを説いた書簡。
「..主の別れ、親子の別れ、夫婦の別れ、いづれかおろかなるべき。..親子の別れこそ月日り隔だつるままに、いよいよ嘆き深かりぬべく見え候へ。親子の別れにも、親は逝きて子は留まるは同じ無常なれども理りにもや。老いたる親は留まりて、若き子の先にたつ情けなき事なれば、神も仏もうらめしや。..」 米569
「..それ針は見ずに沈む。雨は空に留まらす。蟻子を殺せる者は地獄に入り、死にかばねを切る者は悪道をまぬがれず。いかにいわんや、人身を受けたる者を殺せる人をや。但し、大石も海に浮かぶ、船の力なり。大火も消ゆること水の用にあらずや。小罪なれども懺悔せざれば悪道をまぬがれず。大逆なれども懺悔すれば罪きへぬ。..」 米570
『持妙法華問答鈔』
日蓮聖人の印可を受けて日持上人が代筆したと伝えられているもの(異説あり)で、『持法華問答鈔』とも称されている。問答形式で法華経が釈尊一代の真髄である事、修行者の功徳も最勝である事を論じている。
「..只、願わくは経を持ち、名を十方の仏陀に願海に流し、誉れを三世の菩薩の慈天に施すべし。然れば法華経を持ち奉る人は、天龍八部諸大菩薩を以て我が眷属とする者なり。しかのみならず、因身の肉團に果満の仏眼を備え、有為の凡膚に無為の聖衣をつけぬれば、三途に恐れなく、八難に憚りなし。七方便の山の頂に登りて九法界の雲を払い、無垢地の園に花開け、法性の空に月明らかならん。是人於仏道決定無有疑の文たのみあり..」 定280
「..生涯幾ばくならず。思へば一夜の仮の宿を忘れて、幾ばくの名利をか得ん。また得たりとも是れ夢の中の栄へ、珍しからぬ楽しみなり..世間の無常を覚らん事は、眼に遮り耳にみてり。雲とやなり、雨とやなりけん、昔の人は只名をのみ聞く。露とや消え、煙とや登りけん、今の友もまたみえず。我れいつまでか三笠の雲と思うべき。春の花の風に随い、秋の紅葉り時雨に染まる。是れ皆ながへぬ世の中のためしなれば、法華経には世皆不牢固如水沫泡焔とすすめたり。 定283
「..願くは現世安穏後生善処の妙法を持つのみこそ、只、今生の名聞後世の弄引なるべけれ。須く心を一つにして南無妙法蓮華経と我も唱え、他をも勧めんのみこそ、今生人界の思い出なるべき..」 定285
『法華題目鈔』 真蹟断簡 京都本国寺 水戸久昌寺等
著作の宛先は日蓮聖人の母、母と光日尼、日蓮聖人の伯母等と伝えられるが確証はない。熱心な念仏信仰者であった女性に与えられたもので、南無妙法蓮華経の功徳を4段に分かち説明し、念仏信仰を離れ法華信仰に入ることを勧めている。
「..いかにいわんや、法華経の題目は八万聖教の肝心、一切諸仏の眼目なり。..」 米134
.
「..それ仏道に入る根本は信をもって本とす。..」 米135
「..例えば蓮華は日に随いて回る、蓮に心なし。芭蕉は雷によりて増長す、この草に耳なし。我らは蓮華と芭蕉との如く、法華経の題目は日輪と雷との如し。..」 米135
「..さればこの経に値い奉る事をば三千年に一度花咲く優曇花、無量無辺劫に一度値なる一眼の亀にもたとえたり。大地の上に針を立てて大梵天王宮より芥子をなぐるに、針の先に芥子の貫かれたるよりも法華経の題目に値うことはかたし。..」 米136
「..法華経の一一の文字、一字一字に余の六万九千三百八十四字を納めたり。例えば大海の一滴の水に一切の河の水を納め、一の如意宝珠の芥子ばかりなるが一切の如意宝珠の財を雨らすが如し。...爾前の秋冬の草木の如くなる九界の衆生、法華経の妙の一字の春夏の日輪にあひたてまつりて、菩提心の華咲き成仏の菓みなる。..」 米139
「..仏は大雲の如く、説教は大雨の如く、枯れたるが如くなる草木を一切衆生に譬えたり。仏教の雨に潤いて五戒・十善・禅定等の功徳を得るは花咲き菓なるが如し..」 米141
『妙法尼御前御返事』 真蹟 池上本門寺 千葉福正寺
妙法尼が夫の臨終の様子を知らせてきた事に対しての返書。
「..それおもんみれば日蓮幼少の時より仏法を学び候しが念願すらく、人の寿命は無常なり。出る気き入る気を待つことなし。風の前の露、尚 譬えにあらず。かしこきもはかなきも、老いたるも若きも定めなき習いなり。されば先ず臨終の事を習いて他事を習うべし..」 米756
「..法華経は実語の中の実語なり。..法華経は是等の宗々には似るべくもなき実語なり。法華経の実語のみならず、一代盲語の経々すら法華経の大海に入りぬれば、法華経の御力にせめられて実語となり候。いわんや法華経の題目をや。..」
米757
『可延定業御書』 真蹟 中山法華経寺
富木女房尼の病気を慰問し、法華経信仰を説き、四条金吾の医療を受けるようにすすめているもの。『病軽重の事』『依法華経可延定業抄』『定業延命抄』とも称されている。
「..命と申す物は一身第一の珍宝なり。一日なりともこれを延ぶるならば千万両の金にもすぎたり。..」 米371
「..一日の命は三千界の財にもすぎて候なり。..一日も生きてをはせば功徳積もるべし。あらをしの命や命や。..」米372
『富木尼御前御返事』 真蹟 中山法華経寺
富木常忍の母尼(90歳没)の臨終に際し、富木尼が孝養を尽くし、よく看取った事を誉め、成仏疑いなきを事を述べている。
「..矢の走る事は弓の力、雲のゆく事は龍の力、男の仕業は女の力なり。今、富木殿のこれへ御わたりある事、尼御前のお力なり。煙を見れば火を見る、雨を見れば龍を見る、男を見れば女を見る。..」 米561
「..尼御前また法華経の行者なり。御信心 月の勝るが如し、潮の満が如し。いかでか病も失せ、寿も延びざるべきと強盛にをぼしめし、身を持し心に物をなげかざれ。..」 米562
『衣食御書』 真蹟 京都妙蓮寺 他
衣や食物の供養への礼状。
「..食は色を増し、力を伸ぶ。衣は寒さを防ぎ、暑さをさえ、恥を隠す。..人のために火をともせば、人の明るきのみならず、我が身も明かし。されば人の色を増せば我が色まし、人の力増せば我が力まさり、人の命延ぶるならば我が命の延ぶるなり。..法華経は釈迦仏の御いろ、世尊の力、如来の御命なり。...」 米785
『妙心尼御前御返事』 身延曽存
妙心尼は女性信者の一人だが詳細は不明。日興の写本があることから駿河の人と推測されている。尼の夫の病について述べ、法華経によって過去の罪業が消えて、命終しても成仏疑いないことを説いている。
「..この病は仏の御はからいか。そのゆへは浄名経・涅槃経には、病ある人は仏になるべきよし説かれて候。病によりて道心は起こり候か。..」 米541